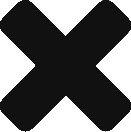衆議院総選挙公約比較-15の争点-シリーズ
今回は【若者政策】です!
給付型奨学金
給付型奨学金とは、返還を不要とする奨学金のことです。
現在、日本では、「貸与」型の奨学金による弊害が社会問題化しています。
奨学金とは、本来学生の学びを金銭面からサポートするものですが、逆に、返済に苦しむ人を増やし、結婚や出産などの人生の大きな岐路にも影響を及ぼしてしまっている現状があります。
この問題の背景には、大きく2つの原因が考えられます。
1つ目は、平均給与が年々減少する一方で大学などの授業料や入学金が高騰していることです。例えば、国立大学における初年度納付金は1970年の1万6千円から、2010年には80万と高騰していることがわかります。さらに、日本学生支援機構の調べによれば、家計からの給付は、2000年度に156万円であったものが、2012年には121万円にまで落ち込んでいます。
2つ目は、家庭からの給付の減少と学生自体の収入の減少により奨学金の重要度が増していることです。これらの状況から、現在では大学生の2.5人に1人(平成18年時点では4人に1人)が奨学金を借りています。
ここで、問題となっているのが、「返したくても返せない」人達の存在です。奨学金の回収状況は、約96%と一見高く見えますが、残り4%、つまり約4万人もの人達が奨学金の返還に苦しんでいるのです。日本では約3人に1人は非正規雇用であり、未返還者の約8割が年収300万円以下であるという事実もあります。
諸外国との比較では、大学教育に関する公費支出(対GDP割合)は、日本はOECD加盟国中最下位となっています。ちなみに、日本では奨学金といえば、「借りる」イメージが強いですが、諸外国では、一般的に奨学金は「給付」を意味します。

これらの事実を受け給付型奨学金の導入と拡充には、日本維新の会が大学授業料の無償化を盛り込んでいることを例外として全ての政党が公約に盛り込んでいるなど、公費支出を教育に配分することによる問題解決の流れが高まっています。
被選挙権年齢引き下げについて
被選挙権とは、参政権のうちの1つであり、簡単に言うと、立候補する権利です。そして、近年活発化しているのが、被選挙権を得る年齢を引き下げようという議論です。現在、日本の法律では、衆議院議員と地方議員(市区町村長含む)は25歳、参議院議員と都道府県知事は30歳と規定されています。
この年齢を海外の被選挙権年齢と比較するとこのようになっています。また、OECD加盟国の79.4%は21歳以下に被選挙権年齢を規定しています。

一方で、被選挙権年齢の引き下げは、人生経験な未熟な政治家を生む可能性があるとの意見もあります。そもそも、年齢によって被選挙権が制限されている大きな理由としては、政治権力は一定の知識と経験をもった人がを持つべきであると考えられていることがあります。
逆にいうと、現在の被選挙権年齢の規定に、明確且つ合理的な理由は存在しないことがわかります。被選挙権年齢の引き下げが検討されている理由は、より若い世代の声を国会や地方議会に反映させるためです。正確には、反映させることを可能にするためです。世代によって価値観や考え方は異なるため、より幅広い世代の代弁者が偏りなく、世代の声を反映できるようにするための動きが加速しています。
実際に立憲民主党と日本のこころ以外の政党は被選挙権年齢の引き下げを公約に盛り込んでおり、被選挙権年齢は引き下げられる方向で議論は進んでいます。その中でも、日本維新の会と共産党は18歳への引き下げを、社民党は一律5歳の引き下げという具体的な年齢を盛り込んでいます。
参考文献
「社会問題化する奨学金」著岩重 佳
「日本学生支援機構について」
この記事は全党の公約を参考に執筆しました。公約へのリンクはこちら