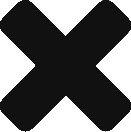はじめに
今週末となった衆議院選挙。その争点のひとつとして憲法改正があります。中でも一昨年に問題となった安全保障法制などが絡む、憲法第9条の問題。
今まで世界情勢やとりわけアメリカとの関係によって憲法第9条の解釈は度々変更がなされてきました。
憲法第9条の解釈はどのような変遷を経てきたのでしょうか?そしてそれに伴う日本の安全保障はどのような変化を遂げてきたのでしょうか?
9条解釈の変遷
憲法第9条の草案時より、日本における自衛的行為の可否に関しての議論が始まります。
▼冷戦下-国連によって担保されるはずだった安全保障
当時制定段階での衆議院において吉田茂首相は、9条第1項と第2項の両方を合わせて読むことで、日本は自衛的な戦争をも放棄するのだという解釈を示しており、その上で日本の安全保障は国連によって担保されると考えられていました。
しかし国連の集団安全保障は、常任理事国に中枢的機能を担わせたことで、冷戦時ソ連が拒否権を発令するなど、機能しませんでした。そのため日本の安全保障は、憲法制定時考えられていた国連による担保はなされませんでした。
更に冷戦構造において、アメリカは日本に共産主義に対する防波堤の役割を求めるようになり、上記のような解釈が徐々に変化していくこととなります。1947年吉田茂首相は、日本は依然として自衛権を保持しているが、戦争・軍備は放棄したので、外交その他の手段の、武力によらない自衛を行うことは出来るという考え方を示しました。
朝鮮戦争が始まると、日本に駐屯していた占領軍が派遣されることとなり、警察予備隊の創設・海上保安庁の増員がなされます。これらは軍備・戦力にあたるのではないかという論争が生じますが、これに対し吉田茂首相は、治安維持目的である警察予備隊は軍隊には当たらないという見解を示します。
▼1951年-サンフランシスコ平和条約締結-集団的自衛権のための取り決め可能に
1951年、サンフランシスコ平和条約を締結したことで、国際的には日本は個別的自衛権および集団的自衛権の行使、集団的自衛権のための取り決めが可能となりました。しかし憲法第9条を掲げる日本では、集団的自衛権に関して、国際法上は保持しているが憲法第9条の制約により行使することはできないという見解がなされました。
●日米安全保障条約締結で米軍との協力を強化
このとき日米安全保障条約も締結され、米軍の日本への部隊展開の継続が決定されました。米国側は東側陣営に対する最前線の一角である日本に部隊を展開し続ける権利を得た一方、日本はその安全保障を米軍の強大な軍事力に頼ることができるようになりました。
●1952年-警察予備隊が保安隊へと改編
翌1952年、警察予備隊令の失効によって警察予備隊は保安隊へと改編されることとなりました。これに伴い、吉田内閣は、憲法が禁止する戦力とは「近代戦争遂行に役立つ程度の装備・編成を具えるもの」であり、それに満たない保安隊は戦力に当たらないという統一見解を発表します。
1953年、朝鮮戦争が終結すると、アメリカは膨大な軍事支出を削減する必要に迫れました。しかしソ連との軍事的均衡を崩さないよう、ニュー・ルック戦略を打ち出し、強力な核戦力による抑止に加え、同盟国各国に防衛力の増強を求めることとなります。
●1954年-日米相互防衛協定締結で自衛隊/防衛庁発足
これによって1954年日米相互防衛援助協定を締結し、日本は自国の防衛力の向上という義務を負いました。保安隊から業務を引き継ぎこととなる自衛隊、そしてその管理を行う防衛庁が発足します。自衛隊は陸・海・空の三部隊から構成される言わば「軍隊的」な組織であり、憲法第9条に違反するのではないかという議論が巻き起こりましたが、岸内閣によって「自衛のための必要最小限度の力は違憲ではない」という新たな9条解釈が打ち出され、その後の内閣の見解の基礎となり、長らく引き継がれることとなりました。
▼1972年-政府統一見解により集団的自衛権は違憲に
その後1972年には政府統一見解がなされ、①日本国憲法は憲法第9条では戦争を放棄しているが、日本の存続と国民の生命を守るための自衛権は放棄していない。②日本国憲法は平和主義を基本原則としているので、国家と国民を守るための自衛の措置は必要最低限のものでなくてはならない。③従って、自衛権を行使する事ができるのは日本に対して直接的な侵害がなされた倍位のみである。とされたことから、集団的自衛権の行使は完全に憲法上否定されているという見方が定着することとなりました。
▼2014年-憲法9条の解釈変更が行われ、集団的自衛権容認
そして2014年、安倍内閣は憲法第9条の解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認するとの閣議決定を行いました。これは1972年の「国民の権利を守るための必要最小限度の武力行使は許容される」との考え方について「今後とも維持されなければならない」と位置付けたうえで「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」が発生し、「我が国の存立が脅かされ、国民の権利が覆される明白な危険」があれば武力行使できると明記しました。「国際法上は集団的自衛権が根拠となる場合がある」との表現で、集団的自衛権の行使容認に加え、集団安全保障も否定しませんでした。
安全保障についての議論
▼日米安全保障条約締結と当初からの問題
国連によっての安全保障はなされず、日米安全保障条約締結で米軍駐屯継続が決まった日本。
しかしこの日米安全保障条約は、締結当時からいくつかの問題点がありました。有事の際の米国の日本への防衛義務が不明確であること、日本国内で起きた内乱に関しても米軍が介入できるとしたこと、アメリカが、日本の防衛以外にも「極東における国際の平和と安全の維持に寄与」する行動であれば日本の基地を使用できることなどは、特に問題視されました。日本の景気の回復、日ソ国交回復の実現、日本の国連加盟によってアメリカへの依存が相対的に低下したこと、ソ連による人工衛星打ち上げ成功により核戦争の恐怖を国民が感じるようになったこと、そして沖縄での大規模な反基地運動「島ぐるみ闘争」での対米感情の悪化などの影響により、日本側は不満を募らせており、日本国内で改定を目指す動きが本格化します。アメリカ側は改定申し入れを数回にわたり拒絶していましたが、1960年改定が実現します。
この新日米安全保障条約締結により、アメリカの日本への防衛義務が明記されることとなりました。同時にアメリカは極東の平和維持のため在日米軍基地の使用が定められました。これによって、この後の日本の安全保障政策の方向性はほぼ決定づけられたと言えます。日本は強力な在日米軍の力で自国の安全保障を確保する代わりに、米軍は冷戦時の東アジアにおける最前線である日本に軍事拠点を確保することとなりました。
1960年代末から1970年代末、米ソ間での関係改善が見られるデタント期に突入したことで、日本はこれまで行ってきた防衛力拡大に歯止めをかけ、ソ連や中国との全面戦争を考慮から外し、限定的で小規模な衝突のみに想定を絞った「防衛計画の大綱」を策定します。国内では、日米条約に頼らない「自主防衛論」も生まれますが、この大綱がデタント期における安全保障政策の軸となりました。
デタント期が終焉を迎え、新冷戦と呼ばれる時代が到来すると、日米同盟の強化として、有事の際の日米間の具体的な行動指針、いわゆる「旧ガイドライン」が策定されます。日本への直接的な侵攻に関する指針であり、それ以外の領域での協力に関しては随時協議することとされました。またこの時期からいわゆる「思いやり予算」として、在日米軍基地の経費のかなりの額を日本側が負担し始めました。
1979年頃から、ソ連の極東における軍備拡大が見られるようになり、日本国内の防衛整備として、有事の際の作戦、指揮、情報の中枢となる中央指揮所構想がまとめられ、作戦研究や、環太平洋合同演習への自衛隊の参加等が行われました。
1981年にはソ連の軍拡に対抗するレーガン米大統領が誕生し、当時の鈴木善幸首相と共同声明を行いました。このとき、旧ガイドラインで規定されていたシーレーン防衛の具現化としてソ連の爆撃機を抑え込める程度の防空力をアメリカ側から求められました。日本側は財政上の点、また国民からの反発が予想されたため、受け入れ困難の姿勢を示しますが、アメリカ側からの圧力の結果、次の中曽根内閣においてシーレーン防衛構想が具現化することとなりました。これにより、自衛隊は魚雷や潜水艦への攻撃に特化した航空機などを多数調達し、対潜水艦戦闘能力が大幅に向上しました。また防空能力確保のため、アメリカ側からイージスシステムも供与されました。しかし、これらの装備をアメリカ軍艦艇の防衛に使用すれば、集団的自衛権の行使にあたるのではないかという懸念がありました。これに対して、中曽根首相はアメリカ艦艇による日本防衛のための来援の阻害に対する救援は、個別的自衛権の範疇であるという解釈を打ち出しました。
冷戦の終結に伴い、日本でも安全保障政策の見直しに着手することとなりました。1994年、細川政権下で設置された防衛問題懇談会によって、樋口レポートが提出されます。ソ連崩壊後、地域紛争や大量破壊兵器の拡散など不透明で予測し難い情勢であるとされ、国連PKO、軍備管理、地域的な安全保障対話を軸に据えた多角的な安全保障協力、また日米安全保障体制の強化が提言されました。
▼1997年-北朝鮮外交の中で「日米新ガイドライン」制定
また1993年以降、北朝鮮の軍事力拡大や中国台湾間での緊張が再び高まったことにより、アジア太平洋地域での紛争への対処として日米安全保障条約が再定義されることとなります。1997年には日本周辺国での有事の対応計画として、「日米新ガイドライン」が制定されました。これに従い、1999年ガイドライン関連法の法整備も行われました。
▼2003年-有事関連三法成立
その後、大きな動きが有ったのは2003年、小泉政権下での有事関連三法成立です。2001年にアメリカで起きた同時多発テロを受けての動きであり、事態対処法、自衛隊法の一部改正、安全保障会議設置法の一部改正から成る法整備です。その中でも事態対処法は有事の際の国や公共機関の責務を定め、武力攻撃に対処するための法的な基盤であると同時に、個別に定める必要のある他の項目についても方向性を示すものです。これらに加え、国民保護のための法整備として有事関連七法が成立し、日本の有事法制は一通り整えられました。しかし周辺事態法で定められた、アメリカによる他国領土での活動に対する後方支援は憲法第9条に、有事の際に個人所有の物品が自衛隊の活動に必要なときは公文書によってその保管を命じられることがある点などは憲法の定める基本的人権にそれぞれ違反するのではないかという批判は根強くあります。
同時多発テロ事件以降のアフガニスタン戦争、イラク戦争、また不況による同盟国アメリカの国際的な地位の大幅な低下、さらには北朝鮮の度重なる核実験や、中国の台頭。これらの世界情勢の変化により、2007年に成立した第一次安倍内閣では、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)を設置し、集団的自衛権と憲法第9条の関係性の再整理を行いました。それまで実行される後方支援が憲法九条に違反しないかどうか、その時々で内閣によって決定がなされており、裁判所の判断が行われたこともなかったため、法的な再整理が必要となったのです。
▼安倍政権がカギとしてきた4つの類型と新武力行使三要件
安保法制懇の設立にあたり、安倍首相は、憲法第9条により大きな制約が存在するものの、対応できなければ安全保障上深刻な問題が発生する、あるいは国際平和への貢献が阻害されるような4つの類型を示しました。
第一に、公海上でのアメリカ軍艦艇の防護の問題です。第二の類型は、アメリカへ向けて発射された弾道ミサイルを日本が迎撃できるかという問題。第三の類型は、国際平和維持活動における武器の使用の問題。第四は、国際平和維持活動で活動する他国への後方支援の問題です。提示された四類型において、集団的自衛権の行使を認めない従来の憲法解釈では、実行的な対応はできません。しかし適切な対処ができなければ日米同盟の信頼性に関わる問題であるとされました。
安倍首相からこのような論点を提示された安保法制懇の報告書では、憲法第9条の解釈に関して、憲法第9条条文の「国際紛争を解決する手段」、保持を禁じられている「戦力」は、個別的自衛権や集団的自衛権の行使、あるいは国際貢献のための実力行使、軍事力の保持を禁止しているわけではないとの解釈、つまり集団的自衛権の行使を可能とするような新たな9条解釈を提示しました。憲法が制定された第二次世界大戦直後とは大きく国際情勢が変化したことを主な理由とされました。
第一次安倍内閣の内閣交代以降には安保法制懇は開催されず、第二次安倍内閣発足によって再開します。2014年の報告書では、2008年の提言より限定的な集団的自衛権を憲法解釈によって認めるべきとの提言を行いました。日本と密接な関係にある国が攻撃を受け、それ自体が日本の安全に深刻な影響をおよぼす際に、攻撃を受けた国の要請や同意に基づいて攻撃の排除に参加できるようにするべきであり、その集団的自衛権は最小限の措置に含まれ得るという主張です。これに加え、武力攻撃には至らない事態への対応体制を整えるべき、在外の日本人を紛争やテロから保護・救助することを可能とするような法整備を行うべきとの提言、更に国連平和維持活動への参加に関する提言も盛り込まれました。
提言を受け2014年7月、安倍内閣は憲法第9条に対する解釈変更による集団的自衛権の行使容認とそれに基づく法整備を行うことを閣議決定しました。
集団的自衛権の行使容認に伴い、これまでの武力行使三要件を見直し、
①我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること。②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと。③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。
という新武力行使三要件を示しました。
▼議論を呼ぶ平和安全法制整備法案
そして、この閣議決定に基づいて2015年5月に国会に提出されたのが平和安全法制整備法案です。これは、自衛隊法、周辺事態安全確保法、武力攻撃事態対処法などの10法案を改正し、新たに平和支援法案を定める法案です。これらの変更点を大きく2つに分けると、直接的に日本の防衛に関わるものと、国連平和維持活動などの国際協力に関わるものとなります。
ここでは日本の防衛に直接関係する変更点を見ていきましょう。
まず重要な点が、武力攻撃事態法を改正した武力攻撃・存立危機事態法の制定です。今回の改正で新たに「存立危機事態」という法的枠組みが作られ、他に適当な手段が無い場合、合理的に必要と判断される限度に限り集団的自衛権の部分的な行使を容認しました。すなわち、日本に直接的な攻撃が無くても武力行使が行えるということであり、先の閣議決定で決められた集団的自衛権の行使容認を法律に落とし込んだものとなります。
自衛隊の任務や組織について定めている自衛隊法も改正され、日本の防衛にあたっている他国の装備も防護することが可能になりました。
また、周辺事態法を改正し重要影響事態法が制定されました。「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」を重要影響事態と名付け、これまでの地理的制約を撤廃。また、これまで後方支援対象はアメリカに限定されてきましたが、今回の改正により「その他国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊」に拡大されました。更に支援内容もこれまで禁じられていた弾薬の提供や給油も可能となりました。
結局、法案は2015年7月16日に衆議院を通過し、9月19日に参議院でも可決、成立しました。
これらは、2016年に新たに定められた防衛大綱にも反映されています。防衛大綱では、防衛力向上、日米同盟を基軸とし国際協調主義に基づいた各国との協力を深化させる戦略を打ち出した。防衛力向上としては、総合起動防衛力の整備を掲げ、陸海空を統合し様々な事態への対処を目指すとし、平時からの情報収集・警戒監視・偵察活動が重要とされました。また、日米関係に関しては日米同盟を世界平和全体の安定と平和に寄与する公共財と位置付け、関係の一層の強化が必要とされました。
自衛隊法からみる自衛隊の扱い
警察予備隊、保安隊、自衛隊、これらの設置と職務、活動内容は、それぞれ法律で定められ、設置の目的も記されています。
警察予備隊令では、「警察予備隊の任務はこの政令は、わが国の平和と秩序を維持し、公共の福祉を保障するのに必要な限度内で、国家地方警察及び自治体警察の警察力を補う」ことが目的とされました。保安庁法では「警察力を補う」という文言が消え、「保安庁は、わが国の平和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため、特別の必要がある場合において行動する部隊を管理し、運営し、及びこれに関する事務を行い、あわせて海上における警備救難の事務を行うことを任務とする」ことが定められました。
そして1954年に制定され、今日まで続く自衛隊法では「自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当るものとする」と任務を定めています。これまでが「平和と秩序の維持」であったのに対して、「我が国の防衛」を明確に任務に定めたことは大きな変化と言えるでしょう。
国際情勢の変化に合わせて憲法第9条の解釈を変更することで、日本はその安全保障体制を整えてきました。
衆議院選挙の争点ともなる憲法改正を考える上で、憲法第9条の解釈をどのように捉えるべきなのか、安全保障法制・自衛隊の存在をどのように考えるべきなのか、問われています。
日本国憲法第9条
一、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
二、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。
各党の政策について
▼はじめに
自民党は今回の衆議院議員選挙の主要公約に、政権党として初めて、9条改正を掲げました。
安倍首相は憲法9条1、2項を維持したまま、自衛隊を明記する提案をしています。自衛隊の明記をする必要はあるのか、それはどんな意味を持つのか、そして、今憲法改正をすることの意味、必要性はあるのでしょうか?
各党の公約・議員の発言、改憲派・護憲派の論拠から、9条自衛隊明記はどのような意味を持つのか、見ていきましょう。
●自民党
公約:「自主憲法の制定」を党是に掲げており、現行憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つの基本原理は堅持しつつ、9条に自衛隊の存在を明記する。
安倍晋三首相は9条1項、2項を維持したまま、自衛隊の根拠規定を追加する提案をしています。改憲時期については今年5月、目標に掲げた「2020年の新憲法施行」には触れず、「国民の幅広い理解を得つつ、初めての憲法改正を目指す」としました。
石破茂氏は2項について「自衛隊、自衛権を否定する考え方だ」としており、改正すべきだとの立場。2項改正の具体案として「日本国の独立ならびに国際社会の平和と維持に寄与するため陸海空3自衛隊を保持する」と挙げています。
党内では石破茂氏の意見に代表されるような、交戦権の否認や戦力の不保持を定める2項の削除に加え、9条の2として国防軍の設置を定める2012年改憲草案にこだわる声も根強くあり、党内で意見が分かれています。
●希望の党
公約:9条含め憲法改正論議を進める
自衛隊の存在は国民に高く評価されており、これを憲法に位置づけることについては、国民の理解が得られるかどうか見極めた上で判断する。現行の安全保障法制は憲法に則り適切に運用する。
小池百合子代表は6日「希望の党の存在が、これからの憲法改正に向けた大きなうねりを作る、そのような役目を果たして行くと思っている」と会見で述べており、また「憲法改正を支持し、改正論議を広く進める」と明記した「政策協定書」を公認候補と交したことで、民進党等からの合流者であっても、改憲反対派は排除されているため、憲法改正には意欲的な立場です。
小池百合子代表は安倍政権で国家安全保障会議の設立などに携わっていたこともあり、外交・安全保障については安倍政権を支持しています。2000年衆院憲法審査会で「日本国憲法はナショナルアイデンティティーを表すものでなければならない」と発言しており、「リアルな安全保障」として2項削除論を展開しています。
しかし結党メンバーであり公約作りにも関わった後藤祐一氏は、「我々は現行の一項二項は変えるべきではない」「今は国民の大多数が「(憲法9条に自衛隊を)位置付けるべきだ」という状況ではない」と述べており、党内で意見が分かれています。
●公明党
公約:多くの国民は自衛隊の活動を支持しており、憲法違反の存在とは考えていない
憲法の3原理を堅持しつつ、必要なら新たな条文を加える「加憲」の立場を維持しています。過去に加憲の対象として、9条に自衛隊の存在を明記する案を検討した経緯もありますが、党幹部は2015年成立の安全保障法制を受け、改正する必要は無くなったとしています。
連立与党として「自民党の9条の考え方は集約されていない。」「自民党内の議論を見守りたい」、「多くの政党が合意形成を図れるよう努めるべき」との立場をとり、山口那津男代表は「今の憲法は優れた憲法だ。国民の理解の成熟がなければ、発議して真を問うのは時期尚早になる。」と述べています。
●日本維新の会
公約:国際情勢の変化に対応し、国民の生命、財産を守るための9条改正
松井一郎代表は「自衛隊を(憲法に)明確に位置づける首相の考え方に反対するものではない」とし、「(憲法を)改正するかどうかは国民の判断だ。共産党や社民党のように国民に尋ねることもなく憲法は今のままというのは無責任だ。時代の変化に合わせて見直すべき。」との考えを述べています。
●日本のこころ
公約:自主憲法制定
中野正志代表は「結党当初から自主憲法の制定を訴えてきた。戦後72年、ここでしっかりと国民の国民による国民のための憲法を制定しなければならない。とりあえずは憲法改正だが、日本のお国柄が盛り込まれた憲法を作らなければならない。安倍首相の時にこれを仕上げたい。」と述べています。
●立憲民主党
公約:専守防衛を逸脱し、立憲主義を破壊する、安保法制を前提とした憲法9条の改悪に反対。領域警備法の制定と憲法の枠内での周辺事態法強化で専守防衛を軸とする現実的な安全保障政策を推進。
安全保障に関しては、専守防衛を超える、集団的自衛権の行使容認に反対・安保法制は違憲であるとの考えであり、武力攻撃に至らないグレーゾーン事態に対応する領域警備法の制定や、憲法の枠内での周辺事態法の強化で対応するとの立場です。
枝野幸男代表は「違憲部分を含む安全保障法制を前提に、憲法に自衛隊を書き込めば、違憲部分を追認することになるので賛成する余地はない。」と述べています。ただし内閣による衆院解散権の制約について改憲の必要性は認めており、国民的な合意が得られれば積極的に議論を進めていくが、現段階ではそこに至ってはいないとした上で、憲法の議論は積極的に進め、国民とともに未来志向の憲法を志向する立場を示しています。
●共産党
公約:憲法9条改定に反対。9条の精神に立った外交戦略で北東アジアの平和と安定を築く
現行憲法の前文を含めた全条項を守るとの立場であり、志位和夫代表は「自衛隊が明記されれば(戦力不保持と交戦権否認を定めた9条の条文が)死文化し、海外でも無制限の武力の行使が可能になってしまう」と述べ、憲法9条を持つ日本こそ、平和的解決のイニシアチブを発揮すべきとの考えを示しています。
共産党は、自衛隊は違憲であるとの立場に立っており、共産党が連立政権を作った場合、「国民の圧倒的多数が自衛隊はもう解消しよう、という合意が成熟するまで、合憲という措置を取」り、「党は違憲、政府は合憲という立場を一定期間取ることになる」としています。
●社民党
公約:憲法改正に反対。9条の平和主義を守り、活かす
平和憲法は変えさせない、として護憲の立場をとり、吉田忠智代表は「9条に自衛隊を書き込むことは、憲法違反の安保関連法にお墨付きを与えることになる。9条改定を阻止して、憲法9条を生かす戦いにしていく。」と述べています。
改憲派・護憲派それぞれの論拠は?
▼改憲派
GHQからの押し付け憲法であるという屈辱感、そして押し付けへの反発から、日本人の誇りや伝統・文化という「国柄」を強調すべきであるとして自主憲法制定運動は進められてきました。自衛隊の存在は70年以上、一度も改正されたことのない憲法と現実の乖離の象徴であるとし、日本の安全保障環境が悪化し、自衛隊の役割が一層重要になる中で、一部の憲法学者が自衛隊を「違憲」と主張するような異常な現状は是正せねばならない、との考えです。
安倍首相は、「(自衛隊の)明記で(違憲か合憲かの)不毛な論争をなくしたい」としており、また安保法制に関しては「廃止すれば日米同盟に取り返しのつかない打撃を与えることになる」と述べています。
改憲派支持者は、安倍首相の9条1、2項維持・自衛隊明記の提案について、「戦力の不保持を定めた9条2項に最大の問題がある。2項を削除して自衛隊や自衛権をしっかり書くのが筋」1(日本会議主導「美しい日本の憲法を作る国民の会」代表)、「9条を変えない限り、国民に自立心が立たない」「何より、憲法改正のための初の国民投票で過半数の賛同を得るのが重要だ。9条2項の削除は後回しでもやむを得ない」2(日本会議神奈川運営委員長)などと述べています。
▼護憲派
制定過程で日本の考え方が取り入れられ、戦後の運用の中で実効性を持って定着していると言え、押し付け憲法だから改憲することに意義があるのではないとしています。9条に関して、「軍事的なものの統制だけでなく、戦後社会の自由の下支えという役割」3を担ってきたとの考えです。
憲法は国家権力の行使を規制し、国民の人権を保障するための規範であり、国の最高法規といて法的安定性が求められます。だからこそ改正には普通の法律以上に厳しい手続きが定められているのであって、他の措置ではどうしても対処できない現実があって初めて改正すべきである、今回公約に出されている改憲項目は、憲法を変えないとできないことではないと考えられています。具体的な不具合から出発せず、改憲それ自体が目的となり、合意を得やすい部分を探すような議論ではなく、改憲を進めるのであれば、その理由と本当に立法で対応できないのかの検討が先にあるのが筋である、との考えがあります。
また「(自衛隊の)明記で(違憲か合憲かの)不毛な論争をなくしたい」ことを9条改正の理由とする安倍首相に対して、「自衛隊は政府が合憲としてきて、裁判所も違憲判決を出していないのに、違憲という学者がいると失礼だというだけで改憲の理由になるのか」4との意見もあります。また、自主憲法制定論や自民党の2012年改憲草案は特定の価値を国民に押し付けるものである、安倍政権での改憲は必要性や優先順位の議論でなく、首相個人の情念に由来する改憲論に基づいている、との批判があります。
安全保障法制に関しては、かなりの部分は個別的自衛権で対応できるとの意見や、「国際経済の相互依存が深まり、他国を侵略して制裁を受ければ損をするだけ」という状況の中で「紛争を避けるには・憲法の平和ブランドの維持強化の方が国益にかなう」5との見方もあります。
▼9条3項を加憲し、自衛隊を明記することに関して、改憲派各党はどのくらいの割合が賛成しているのか?
安倍首相が9条1、2項を維持し、自衛隊の根拠規定を追加することを提案しましたが、この方針については自民党の73%、維新の会70%が賛成を示す一方、公明党では22%、希望の党では38%にとどまりました。公明党の58%、希望の党33%は「9条を改正すべきではない」と否定的な立場をとり、賛否が分かれています。6
▼国際協調主義or平和主義?
国際協調主義とは…
日本は大国として世界の平和に積極的に貢献すべきとする、安倍政権はこの立場です。抑止力が高まり戦争発生に可能性は減るとの考えです。北朝鮮の問題においては、「核・ミサイルの拡散を防ぐ」ことを優先していると言えます。
平和主義とは…
集団的自衛権を認めず、外国の戦争に巻き込まれるのを回避すべきとする立場であり、立憲民主党、共産党、社民党がこの考えに立っています。北朝鮮の問題においては、有事の際にも日本は米韓への軍事的協力を控えれば、巻き込まれるのを避けられるとの考えです。国際協調主義に対して、「紛争リスクの回避を最優先し、一定の譲歩を余儀なくされても対話を重視すべき」との立場です。
▼9条自衛隊明記はどのような意味を持つのか?
●二項死文化とは?
第三項を加えて自衛隊を明記すれば、「二項が死文化する」との声が上がっています。これは、第三項を加えて自衛隊を明記し、二項と抵触する部分が出てくるとされた場合、後から作られた方が生きる「後法優位」の原則から二項は死文化してしまう、ということです。そのため、現在は安保法制改正により集団的自衛権の一部の行使が容認されていますが、一部だけでなく、集団的自衛権を全て認めることに繋がりかねないとの懸念があります。
自衛隊は戦力ではないという現在の曖昧な位置付けをそのまま残すことになる、との批判や、「固有名詞である自衛隊を書き込むことは、自衛隊が極めて正統性の高い国家組織になる一方、法律で設置されていた組織に過ぎない防衛省と上下関係が逆転する」7のではないかとの疑問も上がっています。安全保障法制で変質した自衛隊を9条に明記すれば、安全保障法制の違憲部分である「集団的自衛権の行使容認」を追認することとなるなど、立憲民主党らが訴えられています。更に、「「違憲の疑義を解消する」という政策目標を達成する手段としては過剰、現状を超える意味を持つことになる」8、「中長期的に日本の自主防衛論に発展する恐れ」9があるとの見方もあります。
最後に
現在、安倍首相は街頭演説では全く改正論議に触れないなど、慎重論も強い9条改正への反応を見極めているとみられますが、衆院選の情勢調査結果を受け、自民党内では衆院選の情勢調査結果を受け、秋に臨時国会を収集し、党として憲法9条の改正原案を示す案が浮上しています。
9条改正案を公約に掲げて選挙に勝てば「民意を得た」ということになり、選挙後自公に加え希望の党も加わり安保法容認派が多数を占めた場合、自衛隊の役割が拡大する可能性もあります。
このような議論を、自衛隊員、その家族は「憲法に自衛隊が明記されるということは当然だと思う。ようやく胸を張れる」と考える人や、また「どこまで任務が広がるのかわからない」「今の憲法が歯止めになっていたので家族としても安心していた。憲法を変えることでさらに平和が保てるのかどうか。そのことを考えて欲しい。」と不安に感じる人もいます。10
憲法9条に自衛隊の存在を明記する必要があるのか、自衛隊の明記はどのような意味を持つのか、そして今改憲する必要はあるのかどうか。
憲法9条の解釈や安全保障法制をどのように捉えるのか、これからの日本国憲法・安全保障政策はどうすべきなのか、国民に問われる選挙になっています。
参考資料
・9条ガイドブック
・小谷哲男 シーレーン防衛 日米同盟における「人と人との協力」の展開とその限界 同志社大学58.4
泰明千々和 安保改定における「相互性の確保」と「抑止力の維持」 防衛研究所 2006
・朝日新聞10月19日朝刊
「自国第一か国際協調か」道下徳成政策研究大学院大学教授
・朝日新聞10月17日朝刊
・朝日新聞10月13日朝刊
「(2017衆院選)憲法論戦こう見る 高見勝利さん、横田洋三さん」
・読売新聞10月14日朝刊
「社説 『国のあり方』広く論議したい 自衛隊の位置付けへ理解深めよ」
◎ 引用
1朝日新聞10月12日朝刊
「改憲論議『小池氏と自民共闘も』『9条変える必要』日本会議関係者、期待と不満」
2朝日新聞10月12日朝刊
「改憲論議『小池氏と自民共闘も』『9条変える必要』日本会議関係者、期待と不満」
3朝日新聞10月13日朝刊
「(2017衆院選)憲法論戦こう見る 高見勝利さん、横田洋三さん」
4朝日新聞10月13日朝刊
「(2017衆院選)憲法論戦こう見る 高見勝利さん、横田洋三さん」
5朝日新聞10月19日朝刊
「国益に沿う 平和ブランド」藻谷浩介日本総合研究所主席研究員
6読売新聞10月14日朝刊
「[衆院選2017]希望・維新 互いに連携期待…候補者アンケート 立憲民主は共産・社民と 対決構図 回答に色濃く」
7読売新聞10月7日朝刊
「憲法改正 透明な議論を」井上武史九州大准教授
8読売新聞10月7日朝刊
「憲法改正 透明な議論を」井上武史九州大准教授
9朝日新聞10月19日朝刊
「国益に沿う 平和ブランド」藻谷浩介日本総合研究所主席研究員
10朝日新聞10月6日夕刊
「『憲法に自衛隊明記』現場は OB『合憲と認めて』 衆院選」
(この記事は、大河原櫻 様より寄稿いただきました。)