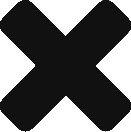衆議院総選挙公約比較-15の争点-シリーズ
今回は【年金】です!︎
年金の役割と制度の概況
まずは年金という社会保険がどのような目的で存在するのか、そして制度の概要を抑えます。
年金保険とは老齢・障害または生計維持者の死亡など、長期にわたる所得の喪失・減少を補填するための定期的な社会保険の1つです。一般的に収入が少なくなる老齢期に適切な収入源を残すとともに、いつ誰に起こるかわからない上記のようなリスクを国民全体でプールするための仕組みです。また、厚生労働省HPでは加えて年金を「社会的扶養」と位置づけ、現役世代と親世代は年金を通して、ともに自立した生活を送れるのだと紹介されています。
日本は国民皆年金制度といって、20歳以上60歳未満のすべての国民が公的年金保険に加入する仕組みを取っています。しかし、公的年金の額は一律ではありません。
なぜなら、現在、日本の公的年金は日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」と、会社などに勤務している人が加入する「厚生年金」の2階建て構造になっているからです。

さらに、公的年金の上乗せとして、企業年金、国民年金基金などの制度があり、年金額を増やすこともできます。自分がどの制度にあてはまるかは、20歳以降の働き方・暮らし方によって決まります。
1階部分の国民年金(基礎年金)は、納付した期間に応じて給付額が決定します。
それに対して、2階部分の厚生年金は、保険料は月ごとの給料に対して定率となっており、働いていたときの給料と加入期間に応じて給付額が決まります。厚生年金は事業主(勤務先)が保険料の半額を負担しているのが特徴です。
(詳しい制度の解説は厚労省「いっしょに検証!公的年金」などをご覧ください。)
争点に入る前に⑴社会の変化
1959年に現在の制度の大元となる国民年金法が制定されてから、日本社会の状況は大きく変わりました。

わかりやすいのは、少子高齢化により人口ピラミッドの形が変化し、全人口に占める現役世代の割合が低下したこと、平均寿命が大きく伸びたことが挙げられるでしょう。
(統計出典:「2015年国勢調査(抽出速報集計)」「1959年国勢調査」((総務省統計局)男女共同参画白書 平成28年版 厚生労働省「平成19年簡易生命表」)
この変化は、現役世代が高齢者を支えるイメージの強い「賦課方式(後述)」を取る我が国の年金制度において、国民の受益と負担のバランスに関する不安を呼んでおり、適切に制度を改めていくことが求められています。
他にも産業構造の変化による働き方の変化、家族関係の変化など社会保障が適応すべき社会の変化には様々なものが挙げられます。
争点に入る前に⑵財源の仕組み

社会保障の給付と負担の現状はこの図の通りです。(参考:厚生労働省「我が国の社会保険制度の構成と概況」平成23年)
2004年の法律改正により基礎年金について、これまで3分の1であった国庫負担割合を消費税増税に伴って、2分の1に引き上げることを定めました。これは、現役世代の保険料負担が過重にならないように配慮しながら、年金給付水準を適正に保つための措置です。
争点に入る前に⑶最近の法改正
前述の国庫負担割合の引き上げなど、近年、年金の制度改革が様々な法案で行われています。それらの政策の是非が公約の比較では登場するのでここで簡単に主な法改正をまとめておきます。

こうした現状に対する各党の政策をCHECK
以上の背景整理を踏まえて、年金の争点は
1 財源確保or支出削減の改革策を適切に選択することで制度を持続可能かつ国民に信頼される形へ
2 老齢所得保障としての年金を機能させる
の2点が大別すると存在します。ひとつずつ各党の政策を見ていきます。
▼財源確保or支出削減の改革策
●賦課方式から積み立て方式への移行(日本維新の会・幸福実現党)

給付保障の方法には「積立方式」と「賦課方式」があります。
賦課方式とは、現在の高齢者に対する年金給付に必要な費用を、その都度、被保険者からの保険料で賄う方式です。デメリットとして、人口構成の影響を受けやすいことが挙げられます。現在の日本はこの賦課形式をとっていますが、積立方式への移行を提案しているのが日本維新の会・幸福実現党です。
積立方式とは将来の自らの給付に必要な原資をあらかじめ保険料として積み立て、運用益を割り増して受け取る方式であり、金利変動の影響を受けやすいです。
少子高齢化によって賦課方式のままでは、ひとりの現役世代が複数の高齢者を支えるイメージがあり、保険料が割高になる・制度の財的持続性が疑わしく、「世代間の受益と負担のバランス」をどう整えるかが課題です。
しかし、少子高齢化で社会全体の生産力が低下すると、積立方式でも、低成長による運用悪化やインフレによる年金の実質価値の低下など、市場を通して影響を受けることになります。また、どのように制度移行を現実的に成立させるのかも重要です。
●支給開始年齢の段階的な引き上げ(日本維新の会・幸福実現党)
日本維新の会と幸福実現党は、支出の削減の策として更に支給開始年齢を段階的に引き上げることも提案しています。
1994年年金法改正によって、支給開始年齢は段階的に60歳から65歳に引き上げられることがすでに決まっています。(2025年に完了予定)段階的な引き上げとは、何十年もかけて行われるものであることをまず理解しておきましょう。
記事の冒頭で確認したように、現代では平均寿命が大きく伸びました。労働者市場が柔軟に高齢者を受け入れる体制を整え、65歳を超えても職につける機会が確保できるのであれば、現代における老齢所得保障の支給開始年齢は引き上げるのがふさわしい可能性もあります。
●富裕層の負担を強める(希望の党・日本共産党・日本のこころ)
財源確保の策として、特定の税機能を強化することで富裕層にもっと大きな負担を求めることを提案しています。
希望の党は所得税増税を、日本共産党は標準報酬額引き上げを、日本のこころは消費税マイレージという独自の税制度を提案しています。
冒頭で説明したように、2階部分の厚生年金に関してはすでに働いていた時の給料の額に呼応して保険料を納める制度です。さらに応能負担の側面を強めていくことに関しては、諸国と比べることによる地理的な相対化と、国内の税制度の全体像との兼ね合いを鑑み、国民の価値観に合うような程度を探るべきでしょう。
●その他
社民党は年金積立金の運用はリスクを鑑みて廃止すべきと述べています。
2016年3月11日に「年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)法」改正案が国会に提出され、積み立て金の積極的な運用が始まりました。その運用資産額は約132兆751億円(2016年度第2四半期末時)に登ります。政府はこの運用利益を年金の財源へ「長期的には」充てることを目指していますが、四半期ごとの決算報告ではプラスマイナス数兆円と不安定な状態であり、これはリスクとも呼べるでしょう。「長期的」投資がうまくいっているのか否かを具体的にはいつどのように評価すると考えるのかが重要です。
自民党は、国庫負担割合を2分の1の中で基礎年金を運用すると記しており、年金の支給水準を安定させながら、保険料を増やしすぎないことを目標としたモデルを提案しています。この実現可能性を近年の法改正の状況からどう捉えるでしょうか?
日本維新の会はさらに、「相続資産への課税ベースを拡大、年金目的特別相続税を創設する」と提案しています。
以上、各党は様々に制度の持続可能性を高める策を持っています。

年金を含め社会保障の議論は税制や財政と共に議論すべきことがよくわかります。次の論点に移ります。
▼老齢所得保障としての年金

(出典:厚生労働省「平成26年度国民生活基礎調査」)
上記の円グラフより公的年金の役割の大きさを確認することができます。高齢者世帯の収入の7割は公的年金であり、年金をもらっている高齢者世帯の6割は年金収入だけで生活しています。自分は年金に頼らず生きるため、保険料を支払わないのだ!と主張する方は、親の老後の生活費を払う覚悟まであるでしょうか?そうでないならば、他の保険者に頼りになっているだけです。
このような統計からも、老齢の所得保障として年金を機能させることは、高齢化が進んだ社会を健やかに支えるため重要であることがわかります。 では各党の策を見ていきましょう。
●必要とする人に対して追加の支援ができる制度を整える(公明党・幸福実現党)
公明党
・「年金生活者支援給付金」(低年金者に最大年6万を恒久的に支給)の前倒し実施
(2012年に年金生活者給付金法がすでに制定されましたが、消費税増税の延期などの影響で施行は2019年からと延期されているのが現状です。)
・障害基礎年金の加算など所得保障の充実に取組む
幸福実現党
・独身老人や低所得な老人にはセーフティネットを整える
これと似た提案として、ターゲティングをした追加保障ではなく全体の所得保障の質を高めようというものがあります。(日本共産党・社民党)
日本共産党・社民党
・年金削減のストップと低年金の底上げによって「最低保障年金制度」を達成する。
(2004年の年金法改正によりマクロ経済スライド方式が導入され、物価指数や人口など社会経済情勢の変動に合わせて支給額も半分以上の水準でという条件付きで自動で変動することとなりました。2017年度の支給額はこの仕組みによって3年ぶりのマイナス修正で、0.1%引き下げられました。財源確保が困難な背景を踏まえて、今後の法改正が年金の削減の方向性へ進まないか懸念する声もあります。)
●被用者年金の拡大(自民党 公明党)
被用者年金とは、雇用されている人が該当する年金であり、現在の制度では 2階部分の厚生年金を指します。2016年の年金法改正により、厚生年金加入の対象者が拡大され、従業員501人以上の事業所においては、週20時間以上就労等の要件に該当すれば新たに厚生年金の被保険者となりました。また、2017年には受給資格期間の25年から10年への短縮が行われ、短時間労働者にもより拡大されるようになりました。
現代の労働形態・労働市場に合わせて、更にこの対象を拡げていこうとする策です。
●選択肢の多様化 (自民党)
健康寿命がのびたことによって、高齢者の定年後の生活に多様性が生まれたことを踏まえ、年金の受給開始時期や額の選択肢を増やすことで実質的な所得保障を柔軟に目指そうという策です。
原則65歳での支給スタートとなる現在も、以下の選択肢があります。
・『60歳から65歳になるまでの間でも、希望すれば給付を繰り上げて受けること(繰上げ受給)ができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、年金額は減額されたまま一生変わりません。』
・『逆に、65歳で請求せずに66歳から70歳までの間で老齢基礎年金を繰下げて請求すること(繰下げ受給)もできます。この場合は、繰下げの請求をした時点に応じて年金額が増額されます。』 (厚労省「いっしょに検証!公的年金」より)
制度の複雑化によって国民の理解がおいつくかなどの不安もあり、情報提供の徹底が求められそうです。
●その他
希望の党は、「年金制度は,生活保護,雇用保険等とともにベーシック・インカムへ移行」
と提案しています。
ベーシックインカム(BI)とは、社会保障の類を一括し、全国民に同額の給付金を定期で支給する新たな所得保障の形であり、諸外国でも検討が進められているところがあります。
貧困の連鎖の防止などを期待されている反面、一個人の人生の時間軸における「再分配」と貧富の間での「再分配」のふたつの社会保障の大きな機能を根本から見直す制度であり、導入にはまだまだ議論が必要でしょう。
社民党は、基礎年金(1階部分)をマクロ経済スライド方式の対象外へすることを提案しています。この自動調整が長期的には実質的な支給額の低下につながり、その減額が所得保障の脅威だと考えているためです。制度がもたらす帰結と、そもそもの目的を達成しているかの二軸で現状の制度を見つめる必要があります。
日本のこころは、税制・年金制度によって非婚化・晩婚化対策をすすめると述べています。

まとめ
国には、市場と人口構成の変化に制度を適応させ、給付と負担の量的調整を果たすことで年金制度運営に関して国民の信頼を取り戻しつつ、老齢期における所得保障としての年金保険の意味を実質化する責務があります。果たせなければ、国民のリスクをプールする年金の制度目的が果たせなくなってしまうからです。
ここ数年は年金法の改正が続き、制度の詳細を理解することは易しくありません。私たち国民も、論点が世代間対立のみに固執し、無益な社会分断を生んでしまわないよう注意する必要があります。制度変化の積み重ねの先に各党がどのような社会保険像をイメージしているのか、本記事で取り上げた二つの切り口から大局をつかむことが重要です。
参考資料
「テキストブック 現代財政学」 著:植田和弘・諸富徹
「はじめての社会保障法」 著:椋野美智子・田中耕太郎
厚生労働省HP 確定拠出年金制度の主な改正(平成29年1月1日施行)
統計データ
「2015年国勢調査(抽出速報集計)」「1959年国勢調査」(総務省統計局)
男女共同参画白書 平成28年版
厚生労働省「平成19年簡易生命表」
厚生労働省「平成26年度国民生活基礎調査」
この記事は全党の公約を参考に執筆しました。公約へのリンクはこちら