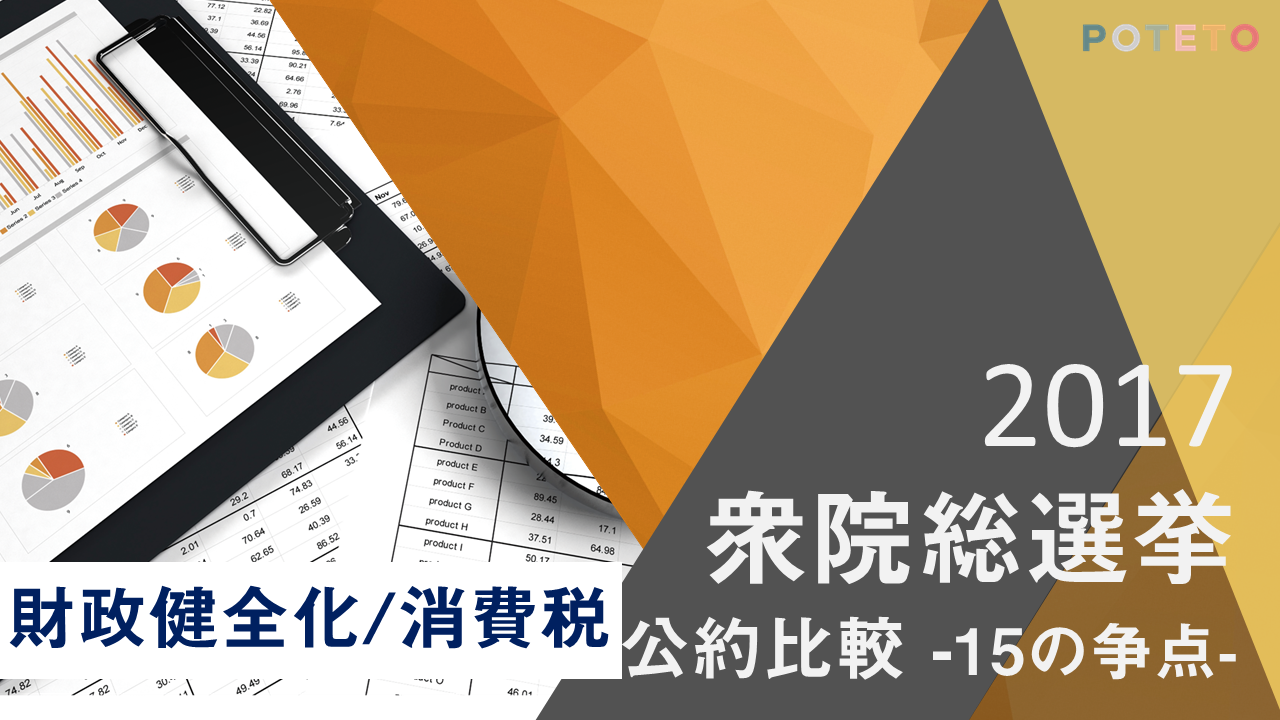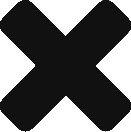衆議院総選挙公約比較-15の争点-シリーズ
今回は【財政健全化/消費税】です!
本記事は二部構成です。
1部ー日本の財政現状について(基礎編)
2部ー財政健全化への姿勢・方法について(本題)
1部ー日本の財政現状について(基礎編)
▼財政の現状について

出典:財務省 一般会計歳入主要科目別予算/ 一般会計歳入主要科目別決算 /一般会計歳出所管別予算 /一般会計歳出所管別決算
まず、日本の財政の現状について、こちらのグラフをご覧ください。
日本という国の、歳出=支出と、税収の推移が示されています。
1989年以降の大きな動きを見ると、歳出は右肩上がりに増加傾向である一方、税収は横ばい傾向が続いています。歳出については100兆円の規模となっています。
出典 財務省 一般会計歳出決算目的別分類/ 総務省統計局 人口推計次に、歳出の増加、税収の減少についてみていきます。
歳出の増加の原因としては様々な理由がありますが、、以下のグラフから分かるように、少子高齢化が背景にあります。

少子高齢化の進行と共に高齢者の割合が増加し、医療費などの社会保障費が急増していることがわかります。
では、税収の減少についてはどうでしょうか。税収の内訳は大きく3つあります。
①所得税 ②法人税 ③消費税 の3つで全体の約80%を占めます。
これらのうち、法人税率は安倍政権下で引き下げられ、税収は増加年もあるものの横ばい状態にあります。消費税は、2019年10月の引き上げが決まっており、これにより5兆増収となり、合計10兆程度の財源となります。
税収を全体としてみると近年少し上向いているもの20年前と比べると横ばい傾向は続いています。
ここまでが、歳出と税収についての整理でした。この図を思い出してください。

出典:財務省 一般会計歳入主要科目別予算/ 一般会計歳入主要科目別決算 /一般会計歳出所管別予算 /一般会計歳出所管別決算
歳出が税収を超えています。この状態を財政赤字と呼びます。新たに加わっている黄色い棒グラフが公債金という国の借金を示しています。
公債金のうち、歳入を補填しているのは「赤字国債」と呼ばれる特例国債です。
財政法第4条には「国の歳出は、公債または借入金以外の歳入を以って、その財源としなければならない」但し「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行し〜できる。」と定められており、この但し書きに基づいて発行される国債を一般に建設国債と言います。
しかし、現実には、歳入欠損が予想される場合にはその年度ごとに特例法が施行されて歳入補填のための国債が発行されてきました。この慣習が続き、額が急増したことで、現在は約865兆円の債務がたまっており、対GDP比でも200%を超えて、先進国の中でも飛び抜けて高い状態です。
財政についての基本事項の確認が終わり、ここからが本題の財政「健全化」の話です。
2部ー財政健全化への姿勢・方法について(本題)
▼財政健全化への姿勢
まず、そもそも債務残高が増加している現状について、どのような議論があるのかご紹介します。まず、問題であるとして財政再建を重要事項と位置づける立場の意見です。
●財政健全化積極派
・国の財政状況が悪くなると、今は円を信頼して国債を買ってくれている(=日本にお金を貸してあげている)人々が、貸しても帰ってこない可能性があり、円への信頼が失われて、国債が暴落して財政が成り行かなくなる。
・今は、なんとかなっていても、将来世代に渡ってこのつけをまわすことは許されない。我々の世代で解決するべき問題だ。
・財政再建を進めるためにも目標設定をすべきである。目標にはプライマリーバランス(=基礎的財政収支)を設定する。
・財政の硬直化が進む
・金利の上昇によって民間の投資が抑制される
●財政健全化消極派
・積極派の言うような、国債が暴落するという話は非現実的だ。国債の9割程度は日本国内で保有されている。自国民がお金を貸しているのにどうして問題が起きるのか。
・将来的には、もちろん解決せねばならないが、増税をしたり歳出をカットしたりすれば、政府規模は縮小し力を失い、日本経済をさらに落ち込ませてしまう。今は、まずはデフレ脱却と経済成長を優先せねば、解消できる債務も解消できなくなる。
・そのため、PB目標は本質的に解決すべき指標ではない。債務残高の対国内総生産(GDP)比率の引き下げを重視する。
▼財政健全化への姿勢ーまとめ
赤字国債を毎年2倍、3倍と発行していこうと主張する人はほとんどいません。
しかし、赤字状態の解消への積極性には開きがあり、その背景にはどうやら、その方法論への認識の違いがありそうです。
財政再建の方法
このように、財政再建をしていくことについては積極性に違いがあるものの、ほぼ合意がとれています。次にその方法に入ります。
まず、シンプルに考えて、財政再建の方法は、「in=税収を増やす」か、「out=歳出を減らす」のどちらかになります。

それでは、in=税収を増やす → out=歳出を減らす
の順に見ていきます。それぞれ4つずつご紹介します。
①-1消費税
 最も私たちに馴染み深い税である、消費税からです。
最も私たちに馴染み深い税である、消費税からです。
これを2019年10月に10%へ引き上げることについて、賛否が衆院選の大きな争点になっています。
まず、消費税という税目自体への評価です。
▼stage1 消費税ってそもそもあり?なし?
●反対派(共産党/社民党)
・年収700万でも年収300万でも必要最低限の生活費が変わらないので、支払う消費税額はあまり変わらないのに収入に差があるという状況になる。とすると、消費税というのは、収入に占める税の割合が高収入者より低収入者のほうが多くなる税であり、その仕組みは社会の経済格差を招いていしまう。(=逆進性が高い税であるといいます。)
・消費税があがると、消費者は出費を避けるようになり、消費は落ち込み経済状態が悪くなる。(実際に、8%への増税後の41ヶ月で家計消費が前年同月を上回ったのは4ヶ月で、37ヶ月はマイナスであった。)
●賛成派(自民/公明/民主など)
・国民が1年間に買うものの量はそれほど変動しないため。他の税目に対して安定的な税収が見込める。
・逆進性は、軽減税率といって、贅沢品は税率10%だが米など生活必需品は税額を据え置く政策によって解決できる。
・確かに経済に響くが、経済状態が良い時にあげれば大丈夫。時期を見てあげるべき。(後述)
次に、消費税自体はありという前提で、「今」あげるべきかあげるべきでないかというstageです。
▼stage2 消費税って2019年10月にあげるべき?あげるべきでない?
●19年10月の引き上げ賛成派(自民/公明)
・経済指標は上向きで、五輪前の好景気が見込める今あげるべき。
・財政再建でなく、社会保障、特に若い世代に還元する割合を予定より増やすことで、国民の負担感を軽減できる。
●19年10月の引き上げ反対派(希望/維新/民主)
・景気実感が伴っておらず、今あげるとデフレ(物価の低下、経済の縮小)招く。今は一旦延期すべき。
さらに、今回の解散の大義とも言われる増税分5兆円の使途の議論が続きます。
▼stage3 消費税の使途ってどうする?
増税分は、財政再建に4兆円、社会保障に1兆円使われるルールになっています。このうち財政再建分の半分2兆前後を幼児教育の無償化や高等教育の負担軽減に変更することの是非を問うということになっています。
●賛成派(安倍首相)
・少子高齢化という最大の課題を克服するために必要な変更で、国民の信を問う必要がある。
●反対派(自民党内にも)
・財政再建を後回しにしていいのか。
・次世代につけを残すような黒字化目標先送りは許されない。
▼消費税の議論まとめ
| 政党名 | ①消費税という税目への評価 | 理由 | 逆進性緩和のための軽減税率の導入 |
| 自民党 | ◎ | 子育て世代への投資と社会保障の安定化とにバランスよく充当し、景気への悪影響を軽減しながら財政再建も確実に実行するために必要 | ◎ |
| 希望の党 | ◎ | – | – |
| 公明党 | ◎ | – | ◎ |
| 日本共産党 | × | 消費税は逆進性のある悪税。 増税後の41ヶ月で家計消費が前年同月を上回ったのは、たった4ヶ月で、37ヶ月はマイナス |
– |
| 日本維新の会 | ◎ | – | 給付付き税額控除 |
| 立憲民主党 | ◎ | – | – |
| 社民党 | × | 格差が拡大する中、逆進性があり、国民生活や景気の悪化を招く | – |
| 日本のこころ | – | – | × |
| 幸福実現党 | × 5%への減税 |
× | – |
| 政党名 | ②2019年10月の10%への消費増税に対しての姿勢 | 理由 | ③消費増税分(約5兆)の使途について、財政再建の比率を4/5より減らす変更への姿勢 |
| 自民党 | ◎ 予定通り引き上げる |
ー | ◎ 使途変更が解散の大きな理由。全ての3-5歳児の幼児教育無償化を支援が必要な所得の低い家庭の子供たちに限って高等教育の無償化も |
| 希望の党 | × 先送り |
ただ増税では消費を冷え込ませるだけだ | ー |
| 公明党 | ◎ 予定通り引き上げる |
ー | ◎ 消費税の使途について、10%引き上げ時の財源の配分割合を変更し、教育の無償化等にも充当できるよう安定的な財源を確保する |
| 日本共産党 | ー | ー | ー |
| 日本維新の会 | × 先送り |
景気の現状を鑑みると増税は凍結すべき | ー |
| 立憲民主党 | × 先送り |
増税を予定通り実行することは国民の理解を得られない | ー |
| 社民党 | ー | ー | ー |
| 日本のこころ | × 先送り |
消費税の再増税を当分の間停止する | ー |
| 幸福実現党 | ー | ー | ー |
以上の図表を見ていただくと分かるように、今回の衆院選での争点としては、増税分の使途ではなく、実際には増税の是非を問う構造になっているのがわかるかと思います。
次に、消費税以外で、税収を増やそうという3つの方法をご紹介していきます。

①-2 法人税・所得税率の引き上げ
●賛成派(共産党社民党)
・法人税率は安倍政権下で30%から23.4%にひき下げられている。国民負担を求める前に、お金をもっているところからお金をとるべきだ。再分配政策が求められる。
●反対派(他)
・法人税・所得税をあげると大企業や富裕層が国外へ出ていってしまい、国内が空洞化してしまう。
・法人税をさげることで、経済がよくなり結果的に税収は増えている。
①-3 内部留保への課税
企業が得たもうけのうち、賃金upにも新たな製品開発、事業展開にも使わずにためているお金を内部留保といい、これが406兆円にのぼります。
これを税目として位置づけようと提案しているのが希望の党です。
●賛成派(希望)
・内部留保は活用すべき。
・新たな税のありかたを模索する段階であり、そのための提案。
●反対派(その他)
・法人税と二重にとってしまう二重課税の可能性が高く、税のとりかたとしてよくない。
・(消費税との対比において)経済状況によって大きく左右されて安定的な財源となりえない。
・そもそも内部留保に課税するという発想が筋違い。そもそも、内部留保という言葉や項目は、会計上存在しない。
①−4 経済成長や景気回復による税収増加
最後に、経済成長、景気回復=内需拡大により税収を増やしていこうという考え方です。
これは多くの人々が前提として認識している財政再建の方法です。
ただし、この税収増加というのを一体社会のどの部分において引き出そうとしているかのスタンスが異なります。
●まずは上から派(自民/公明)
・まずは金融政策や財政政策で株価があがり円安になることで、大企業は潤う。まずその税収は増えるし実際に増えている。
・また、その影響は企業の賃上げなどの形で順次一般国民に波及していく。(これをトリクルダウンという)
●まずは下から派(民主/共産/社民)
・安倍政権のいうトリクルダウンは起きていない。国民の生活実感はどんどん悪くなっている。
・国民の生活実感をあげる政策をうち、景気を良くし、国民に生活への安心感を与えることで、GDPの約6割を占める内需を掘り起こすことが必要だ。
両者の経済政策から社会保障まで含めた、政治観の違いから、その先にある、どこから税収増を期待するのかということが透けて見えるのではないでしょうか。
経済政策については、詳細はこちらをご覧ください。
ここまでが、inを増やす話でした。次にoutを減らす話に入ります。

②-1 政治にかかるお金を減らす。政治のスリム化
議員報酬の削減や、議員が使うことのできる文書交通費などの歳費の削減をするという支出削減の方法です。 議員報酬の削減のために議員定数を減らし、さらには参議院を廃止して一院制にするといった政策までこの文脈で扱うことができます。
●賛成派(維新/希望)
・まずは議員が身を切る前に、国民に負担を求めるなどもってのほかだ。
●反対派
・一定のお金があるから議員として十分な活動をして国民の期待をうけることができる。お金がないと国家議員としての職責を果たせない。
②-2 行政の使うお金を減らす。行政の効率化・スリム化
次に、行政の効率化やスリム化による経費削減です。
●賛成派
・国民のお金で行政がムダなことをするわけにはいかない。
(維新)
・行政の縦割りを排除し歳入庁を設置して、効率的な財政を実現する。
・国、地方の財政制度に発生主義会計と複式簿記を導入して、会計を民間水準にする。
・「N分N乗方式」を導入する。
(希望)
・国有資産の売却をする。
・政府系金融機関の廃止に伴う貸付金の回収をする。
●反対派
・予算をカットしたり、民営化すると行政サービスの質が下がってしまう。
・現状の行政は高い質を保っており変革の必要性はない。
②-3 公共事業費や防衛費など特定分野の経費削減
次に、特定分野の経費削減です。
●賛成派(共産ー両者ともに 希望ー公共事業のみ)
・当該支出は不要である。
・公共事業については、古い政治と建築業者の間でのしがらみから不要なものも多くされており、見直す必要がある。
●反対派(他)
・いずれも必要であり、いたずらに削減の対象とするのは間違っている。
②-4 社会保障の仕組み、支出の見直し
最後にここでご紹介するには紙幅が足りなさ過ぎるので大幅に割愛いたしますが(しかしこれこそ最大のポイントになりうる可能性があるのですが)、財政再建と密接に関係する話です。
支出増加が社会保障によるところが多い以上、その増加幅を抑えるような政策は今後議論されていくものとみられます。社会保障とひとくくりに言っても、年金や医療保険、介護保険など様々な社会保険や制度が含まれるため慎重に争点を見極める必要が有ります。いくつか例をあげておくと、年金の受給開始年齢の引き上げや応能負担の拡充などが提言されています。
以上、財政再建の方法についてまとめると以下の表のようになります。
社会保障については、表にまとめられないため省略しています。
消費税以外の財政再建の方法について
| 政党名 | 再建方法① 消費増税以外での歳入増加 企業、個人のお金をより多く徴収する |
再建方法② 歳出削減 政府支出を削減するなど政府のスリム化 |
財政再建の目標 |
| 自民党 | 言及はあるが具体策はなし | 言及はあるが具体策はなし | 黒字化する目標は引き続き堅持するものの、2020年までの黒字化は先送り |
| 希望の党 | <企業へ> 内部留保への課税 |
•財政支出の削減 •公共事業など歳出削減 •国有資産の売却 •政府系金融機関の廃止に伴う貸付金の回収 |
達成が可能な現実的な目標に訂正し、経済に対する負のインパクトを緩和する |
| 公明党 | ー | ー | ー |
| 日本共産党 |
<企業へ> |
ー | ー |
| 日本維新の会 | ー | •行政の縦割りを排除し歳入庁を設置 •「N分N乗方式」の導入 •国、地方の財政制度に発生主義会計と複式簿記を導入する •国会議員歳費を3割削減・議員定数を3割削減 |
経済成長/歳出削減/歳入改革のバランスのとれたプライマリーバランスの黒字化の目標を設定する |
| 立憲民主党 | <個人へ> 所得税・相続税、金融課税をはじめ、再分配機能の強化 |
ー | ー |
| 社民党 | ー |
専守防衛をはるかに超えて拡大する防衛費の縮減など裁量的経費の見直し |
ー |
| 日本のこころ | ー | ー | ー |
| 幸福実現党 | ー | ー | 30年間で政府の借金解消を目指す |
終わりに
財政は外交と並び、国の要ともいいます。また、経済や社会保障とも密接に関連する、難しい領域でもあります。
この記事を理解や整理の助けとして、しっかりと将来に渡る財政状況を考える機会をとって、長期的な視点にたった投票というのを追求してみてください。
参考資料
財務省 統計
財務省 日本の財政関係資料(平成28年10月)
アベノミクス「3本の矢」 首相官邸
この記事は全党の公約を参考に執筆しました。公約へのリンクはこちら