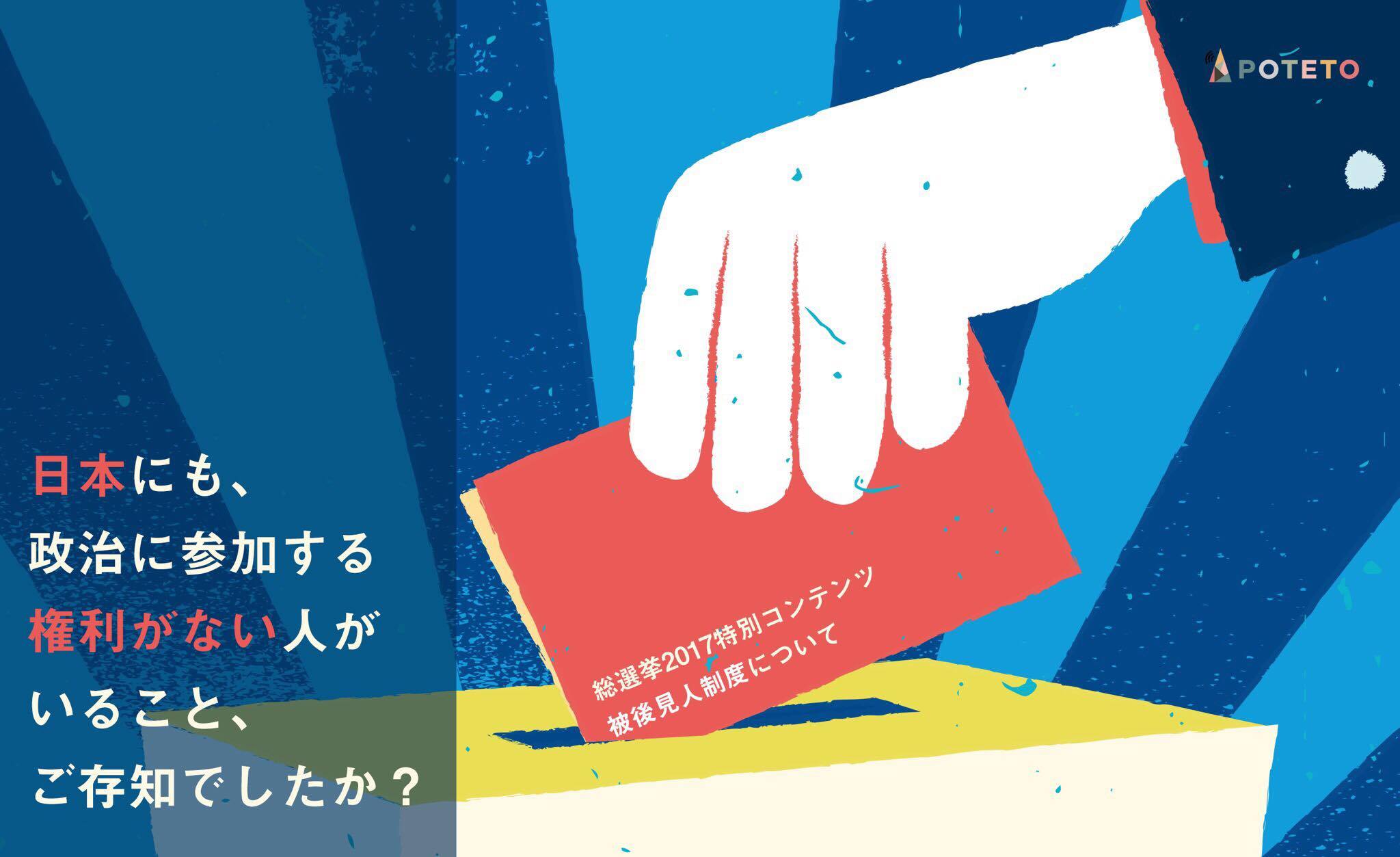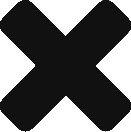ポイント
・戦後になってもなお「選挙権」を与えれらない人たちがいた。
・2013年に選挙権を獲得するにいたった、被後見人の存在
・受刑者の選挙権は今もなお認められていない。
18歳選挙権に沸いた2016年の参院選は過ぎ去り、我々の目の前には来たる衆院選が待ち受けます。
昨年「選挙権が与えられる!よっしゃラッキー!」と意気込んで投票に向かった18歳、19歳の方も多いことでしょう。
でも、そのように選挙権が与えられた方もいれば、その影には与えられない方、もしくは最近まで与えられていなかった人々もいることを、ご存知でしょうか。
本日はそんな選挙権の移り変わりと、様々な試みについてみてみましょう。
選挙権の移り変わりをざっとおさらい
まず今の日本の衆議院選挙・参議院選挙において選挙権が与えられる条件は、
「日本国民で満18歳以上であること」(※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。出典:総務省)
です。しかし、ここまで多くの人に選挙権が与えられるまでには長い道のりがありました。
★簡単年表★
1889年 25歳以上の男子 直接国税15円以上の納税者 公開制 人口の1%
1900年 25歳以上の男子 直接国税10円以上の納税者 秘密投票 人口の2.2%
1919年 25歳以上の男子 直接国税3円以上の納税者 秘密投票 人口の5.5%
1925年 25歳以上の男子 納税要件の撤廃 人口の20%
1945年 20歳以上の全ての男女 人口の48%
(出典:18歳から選挙権)
徴兵制が男子全員に課されていた当時、「国のために命を懸けて戦っているのに選挙権がないなんておかしい」という意見が広がり、全国に「普選運動」が巻き起こりました。また、改めて驚くべきことに、女性に参政権が与えられたのは戦後。女性の参政権獲得に向けては、有名な平塚雷鳥をはじめ、数多くの女性運動家が活躍しましたが、その多くが弾圧を受け、無念の中死んでいきました。
このように、今のような比較的平等な参政権獲得の陰には、長期にわたる多くの人の犠牲があったというわけです。
戦後もなお選挙権を持たなかった人たち

とはいえ、こうした「納税額」や「性別」のよって選挙権が与えられてこなっかった事実は、皆さんもご存じの歴史上有名な話です。
しかし、実はこの歴史には続きがあります。驚くべきことに、戦後1945年以降もなお、理不尽にも選挙権を制限されていた人がいることを、皆さんはご存じでしょうか。
まずは、「破産者」「貧困で生活扶助を受給していた人」です。これらの人は1945年(昭和20年),1947年(昭和22年)の法改正等で削除されるまで、選挙権がありませんでした。また、「心神耗弱者,聾者(口がきけない人), 唖者(聴覚に障害がある人), 盲者」も、1950年(昭和25年)に法改正で削除されるまで、同様に権利を有しませんでした。
つまり、戦後比較的平等に広く与えられるようになったと思われている選挙権ですが、実は理不尽にも選挙権が制限されている人はいたのです。
最近まで選挙権が無かった、成年被後見人って何?

そんな中、最近ようやく選挙権を持てるようになった人たちがいます。2013年に最高裁で違憲判決が下り、法改正によって選挙権を得た「成年被後見人」と呼ばれる人たちです。
成年被後見人とは、
「精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人。本人の代理として成年後見人が財産管理などを行う。」(出典:コトバンク)
とされています。
このように、成年被後見人とみなされた人が、成年後見人によって補助される制度のことを「成年後見制度」と言い、この制度は2000年に開始しました。それまでは禁治産制度と呼ばれており、明治以来のこの制度では、心神喪失状態(精神障害などによって自分の行為の結果について判断する能力を全く欠いている状態)の人に裁判所が禁治産と宣告すると、さまざまな法律行為が制限されるようになっていました。選挙権を含め、約150にも上る「欠格条項」があり、「ただし禁治産者を除く」というような条文がさまざまな法律に書き込まれていたのだそうです。
しかし、90年代に入ると次第にノーマライゼーションの考え方が世界各地で生まれるようになり、たとえ判断能力などが鈍る人がいたとしても、その人たちの行為を「制限」するのではなく「支援」していくべきだという考え方が広まりました。日本もそれにならって、90年代後半に成人後見人法が議論されていく中で、法務省は各省庁に「欠格事項」の見直しを打診しました。それでも結局は時間切れ状態で法改正までには至らず、2000年に今の「成年後見人制度」が出来あがったというわけです。こうしてそれ以降も、知的・精神障がい者や認知症患者、心身喪失状態にある人は選挙権を剥奪され、その他のさまざまな条項で制限を受け続けて来ました。
それでもここに不平等を唱える人がいなかったのは、この制度自体を使う人があまりおらず、少数派の意見だったためです。
転機をもたらしたのは06年の障害者自立支援法
そんな状況に転機をもたらす出来事がありました。
それは、それまでの障害者や高齢者の様々な福祉サービスは行政が「措置」するという考え方から、本人の自己決定権を尊重して「契約」に変えていくべきだ、という考え方の移行です。こうして2003年に支援費制度としての契約概念が入り、06年には障害者自立支援法に移行することになりました。こうして、障害者や高齢者などが「契約」をしなければならないとなると、成年後見人(彼らを支援する人)のサポートが必要となってきます。こうして、06年には障害者を中心に約1万件もの成年後見の集団申立てがあったと見られており、制度の利用者が一気に増えました。
このときに、それまでは「被後見人」にはなっていないので選挙に行くことができた障害者の方が、福祉などのサービスを使うために後見人を付けた途端に選挙に行けなくなるという事態が数多く発生したとされています。
被後見人が選挙権を獲得する決め手となった裁判
自明の事実として不平等さはあったものの、国はなかなか動きませんでした。こうして2013年、成年後見人が付くと選挙権を失うとした公職選挙法の規定は違憲として、茨城県牛久市の女性が国に、選挙権の確認を求めた訴訟の判決が行われました。この裁判で、裁判長は「成年被後見人から一律に選挙権を奪うことは、許容できない」などと述べ、同規定を違憲で無効と判断し、女性の選挙権を認める判決を言い渡しました。これにより、公選法改正が進められ、2013年3月にはそれまで選挙権を剥奪されていた13万人以上の方々が選挙権を回復したのです。
この改正を受け、総務省は公平な投票の実施を確保するために、代理投票において選挙人の補助をすべき者は投票に係る事務に従事する者に限定されるとともに、病院や老人ホームで行われる不在者投票では、外部立会人をつけるなどの努力義務が設定され、仕組みづくりが進められました。
では選挙権がある今、どう投票するのか
被後見人の方が投票するには、期日前投票、不在者投票の大きく2つの方法があり、ほかの人たちと変わりません。変わる点はというと、その際の手段と場所です。
①都道府県の選挙管理委員会が指定した病院老人ホーム等で不在者投票が可能
文字通り、指定の病院に入院されている方、施設に入所されている方は、そこの病院長等の不在者投票管理者のもとで投票を行うことが出来ます。また、要介護5等に該当する方は、事前に選挙管理委員会へ申請が必要にはなりますが、郵便等による不在者投票制度を利用できます。
②代理投票/補助を頼むことが可能
代理投票とは、心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載することが出来ない場合に、その選挙人本人の意思に基づき、候補者が代わって投票用紙に記載する制度のことです。この代理投票を行う場合は、受付で必ず障がいや認知症の旨を伝える必要があります。申請の際は紙でも口頭でも構いません。申請を受けると2名の補助者がつくことになります。また、もし代理でも、付き添いの方が書き込みを手伝ったりすると無効となってしまいますので注意が必要です。
このように、制度上は被後見人の方々も投票が可能にはなったものの、まだまだ投票制度自体のバリアフリーは進んでおらず、今後は制度があるだけで利用されないのを防ぐべく、策を練っていくことが必要です。
まだ今も選挙権がない人たち
このように、戦後まで選挙権を持たなかった人、最近にやってようやく選挙権を持った人を見てきましたが、実はこの他に、日本にはまだ「選挙権のない人」が存在します。以下に、本来は選挙権を持っているのに失ってしまう条件を見てみましょう。
★選挙権を失う条件6つ★
◎禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
◎禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
(刑の執行猶予中の者を除く)
◎公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者。
◎選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
◎公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
◎政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者
(出典:総務省)
以上6つのうちどれかに抵触すると、選挙権を失ってしまうというわけです。
この中に含まれている「受刑者」の選挙権はく奪については、すでに2013年に大阪高裁で違憲判決が出ており、判決文で裁判長は、「過失犯など、選挙権の行使とは無関係な犯罪が大多数だ」と述べ、「受刑者は著しく順法精神に欠け、公正な選挙権の行使を期待できない」とする国の主張を退けています。
一方で、2016年には合憲判決も出ており、広島地裁で行われた裁判で、裁判長は「社会から隔離された刑事施設で処遇される刑の性質上、刑罰に伴う制裁として受刑者の選挙権を制限することは選挙権の重要性を考慮した上でも一定の正当性、合理性がある」と述べています。このように、合憲判決と違憲判決が各所で出されている状態で、立法的な解決には至っていません。
国際的には受刑者に選挙権を認める方向にあるため、国際基準に合わせるのか、それとも国際基準とは一線を画すのか、が今後重要になってきます。
他にも、「日本に帰化し、住民票を移して3か月を満たない者」は投票権を有していません。つまり、外国籍の帰化者は帰化しても3ヶ月間は投票できない、というわけです。
なぜこのような制限があるかというと、3ヶ月という期間が、一方の国で投票してさらにもう一方の国でも投票をするという二重投票を無くし、選挙の公正さを担保するために必要な技術的な期間とされていたからです。しかしこの制度が出来てから50年以上経っており、制度自体が時代に合わなくなってきているとの見方もあり、今後の議論に注目です。
投票権の歴史から考える「1票」の意味

これまで、選挙権がどのようにより多くの人に与えられてきたかを見てきました。
ノーマライゼーションが進んだ今、選挙権を持つことは多くの人にとっての当たり前となったように思えます。しかし、その影には「平等」を叫ばれるようになった戦後においてなお、理不尽にも選挙権を持っていなかった人や、最近になるまで選挙権を持っていなかった人、そして未だ選挙権を持てずに戦っている人がいます。
たかが選挙権、と思われる方もいるかもしれません。ですが、今一度、この記事を通して選挙権が持つことの意味を考えてみてください。
裁判をしてまで、選挙権獲得のために戦っている人たちがいるのはなぜか。国政に参加する、国の未来を決める当たり前の権利である1票を、その国に住んでいてこれからも住み続けるのに与えられないことが、その人にとってどんな意味を持つのか。
「平等」や「民主主義」という言葉が使い古され、当たり前のように使われるようになった今だからこそ、この記事を投票の意味を考えるきっかけにしていただけることを願っています。
最後に、成年被後見人に選挙権が無いことを違憲とした最高裁判決での判決文を引用して終わります。
「後見開始の審判を受け、 成年被後見人になった者であっても、我が国の 『国民』 であることは当然のことであり、…(中略)…自らを統治する主権者として, この国がどんなふうになったらいいか、あるいはどんな施策がされたら自分たちは幸せかなどについての意見を持ち、それを選挙権行使を通じて国政に届けることこそが、 議会制民主主義の根幹であり生命線であるからにほかならない。」