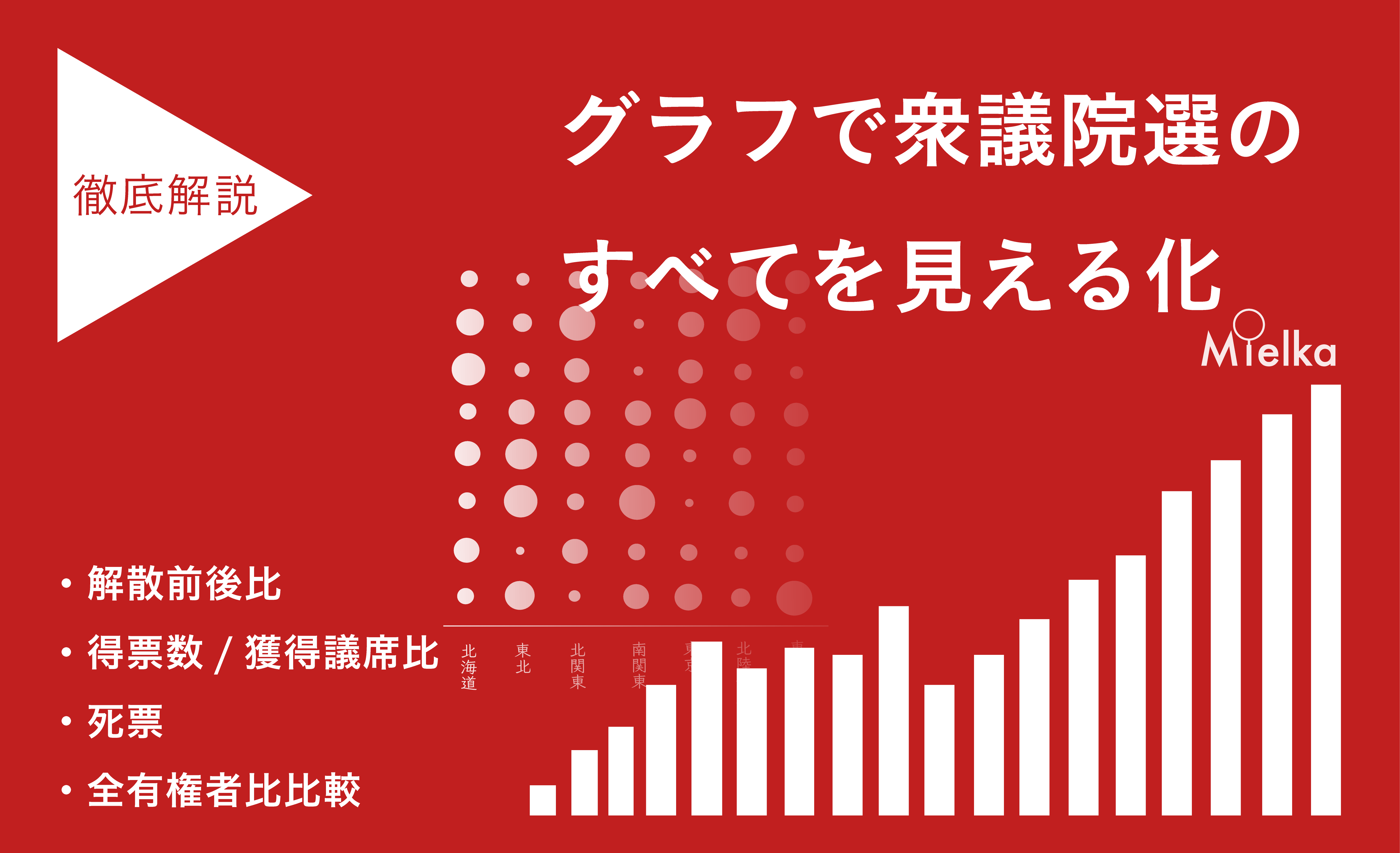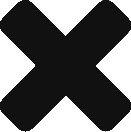(少し読み込みに時間がかかりますがそのままお待ち下さい。。!!)
10/22投票の衆議院選挙の結果を、動くグラフで可視化しました。
分析項目は以下の7つです。
①各党議席数
②小選挙区/比例区別分析
③死票
④男女比
⑤年齢比
⑥前職/新人比
⑦国民の声
*なお、「Mielkaラボ」の所有するデータの制約上、⑤については「前職」を小選挙区立候補者のうちの前職に限った分析です。つまり引退議員や比例単独で今回立候補した議員は除いた数が母数となっています。(非常に細かいことですが念のためのお断りです。)
まずは、基本事項から抑えていきます。
①各党議席数
まず、全体として、議席数が減っています。これは定数が10削減されたためです。
〜タップで議席数が表示されます!!〜
加えてこちらのグラフを左右に切り替えていただくと、大きな変化が一つと、残りはほとんど変化していないことにお気づきになるはずです。
と言われてもわかりにくいと思うので、上の図表を読み解くためのヒントとなる数字はこちらです。
これらを棒グラフにしてみました。棒をタップすると何を示しているか表示されます。
自民・公明の与党は、憲法改正の2/3ラインを超えて、自民は単独で1/2を超えています。このあたりは前回の結果と変わりません。
希望が減らし、立憲民主が増やしました。共産と維新は共に減らし、単独での議案提出の可能な議席数には達しない見込みです。
上の半円グラフに戻って、体感してみてください。
②小選挙区/比例区別分析
まずは、小選挙区についてです。グラフを左右に切り替えてご自身で分析してみてください。得票数と獲得議席数の関係が分かります。
以下がそれを並べたものです。
2位以下の得票が、バッサリと切られる小選挙区制ならではですが、第一党は得票数に比べて議席数で割合を増して、第二党以下は軒並み減らしています。
自民党は得票では過半数に達していません。
次に比例区をご紹介します。比例区の獲得票数と、獲得議席数を表しています。
最も民意を反映するとされる比例区では支持政党の割合はこのようになりました。
以下がそれを並べたものです。
小選挙区との対比で見た時に、こちらのほうが素直に全体比を反映していることが分かります。これが、比例区と呼ばれる由縁です。
③死票
関連して、こちらは上が小選挙区の当選者得票数、下が死票(=落選者得票数)を表しています。
こうしてみると、全体の48.24%の国民の声は汲み取られずにいるとも言えます。しかし多数決によって「決める政治」は必要であり、このジレンマは非常に難しい問題です。
④男女比
まずは、グラフを操作してみてください。
以下がそれを一覧化したものです。
日本国民全体を見ると、女性が50%をやや超えているのですが、全候補者中では17.7%、前職議員中だと、9.3%にとどまっています。
そして、選挙後全体は10.53%です。
やや増えましたが、日本国民の割合と比べると大きな開きがあります。
次に、政党ごとの男女比です。
共産党→立憲民主の順に女性割合が多く、1議席のみ獲得の社民を除くと、自民党→希望の党の順に女性割合が少ない結果です。
⑤年代比
年代比です。よくよく観察してみてください。
一覧にしたのが以下です。
被選挙権が25歳以上に制限されていることにより、0~24歳が2つめのグラフ以降には入っていないことが分かります。
また、被選挙権年齢のある人々のうち、25~39/70歳以上については、候補者に占める割合が少なくなっているのに対して、40~69までが全体の8割を占めるという構成になっています。
選挙後議員で見ると、25~29歳の議員はおらず、最年少は31歳です。また全体的にやや年齢層があがっています。
次に、党ごとの年齢比です。
40代以下で見ると、希望→維新→立憲民主 の順に割合が多くなっています。
対して、共産党→公明党→自民党の順に40代以下割合は少なくなっています。
⑥前職/新人比
グラフを動かすと、一目瞭然の特徴があります。
自民/公明/共産/社民の前職多数に比較して、立憲民主の新人比率の高さが目立っています。
⑦国民の声
①〜⑥が全て投票結果をベースにした可視化に対して、最後にその可視化から抜け漏れている人々の可視化です。グラフをタップすると何を示しているか表示されます。
もちろん第一党自民党を支持する方が多いものの、さらに多い国民がいます。全体の半分程度が、棄権=無視しています。この現実は非常に重い現実です。
終わりに
本記事では、出来る限り直感的に衆院選/国会/議員について「感じて」いただき、そしてちょっと「考えて」ほしいという想いを込めて6つの角度からの分析を試みました。
今後も、JAPAN CHOICE/Mielkaラボでは、人々がどうすれば「楽に」合理的な判断=投票 を下すことができるのかを探求し、そのような環境を整えるために、精一杯取り組みを進めていきたいと決意新たにしています。
分析記事は続編を予定しています。分析項目のご提案をいただけましたら精一杯お答えさせていただきます。よろしくおねがい致します!!