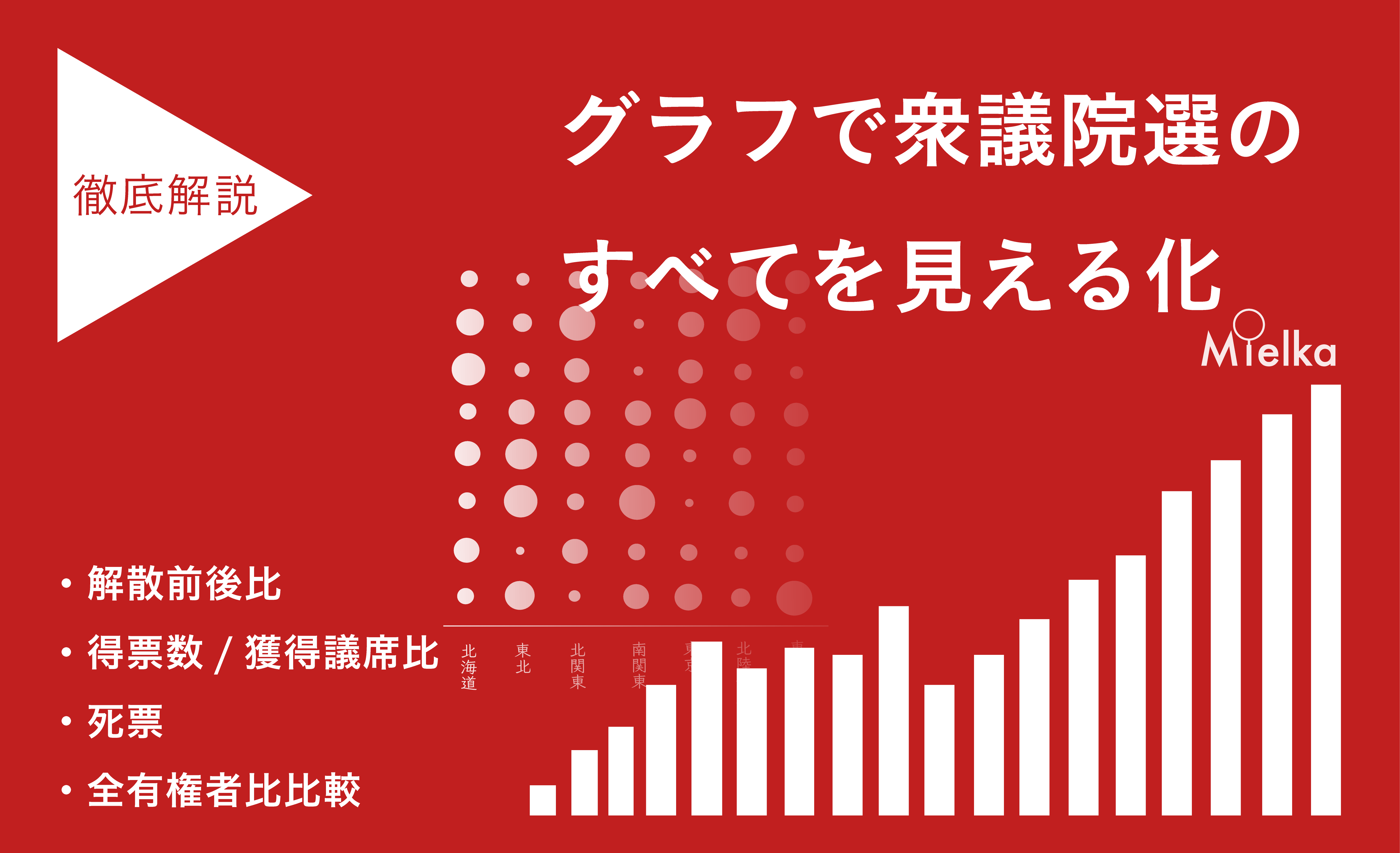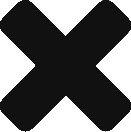(少し読み込みに時間がかかりますがそのままお待ち下さい。。!!)
本記事では、今回の衆議院選挙の立候補者について分析を行っていきます。
分析項目は以下の5つです。
①男女比
②年代比
③地域比
④拡大意欲比
⑤比例単独比
*なお、「Mielkaラボ」の所有するデータの制約上、①~③については小選挙区立候補者に限って分析していることを予めお断りしておきます。
①男女比
まずは、ぽちぽちと左右に切り替えてご自身で分析してみてください。
〜ここで注意! 前職とは、解散前に議員だった方々を言います! 1ヶ月前まで議員だった方々です!!〜
以下がそれを一覧化したものです。
日本国民全体を見ると、女性が50%をやや超えているのですが、全候補者中では16.7%、前職議員中だと、8.6%にとどまっています。
続いて、政党ごとに見ると、立憲民主党→公明党(→無所属)→共産党の順に女性候補者割合が多いです。
対して、幸福実現党→社民党→希望の党の順に女性候補者割合が少ないです。
さて、こちらは新人前職元職での女性比率です。
前職より新人の女性割合が高くなっています。
社会の様々な領域に女性が進出し、もはや女性進出という言葉自体が古くなりつつあるこの時代に、政治における女性の進出が、一歩進む兆しともいえるでしょう。
②年代比
年代比について傾向を探ってみてください。
グラフ化するとこうなります。
被選挙権が25歳以上に制限されていることにより、0~24歳が2つめのグラフ以降には入っていないことが分かります。
また、被選挙権年齢のある人々のうち、25~39/70歳以上については、候補者に占める割合が少なくなっているのに対して、40~69までが全体の8割を占めるという構成になっています。
前職議員で見ると、25~29歳の議員はおらず、また全体的に年齢層があがっています。
続いて政党ごとの年代比です。
一覧にすると以下です。
20代と30代で見ると、幸福実現党→日本維新の会→希望の党 の順に候補者割合が多く、社民党→自民党→立憲民主党 の順に候補者割合が少なくっています。
前職元職の候補者割合の多い政党のほうが年齢構成が高くなっていることが伺えます。
上記少し簡略化してわかりやすくしたのが以下です。中心線(厳密には中心ではありませんが)の動きで、各政党の傾向を体感してください。25〜49歳と50〜89歳で分かれています。
最後に、現職/新人/元職間での比較です。
現職より新人のほうが全体的に年齢が低いことが分かります。
基本的に、当選して議員を務めているものが年齢が上なのは当然と言えば当然ですが、「上の年代から上の年代へ」より、「上の年代から下の年代へ」の交代を求める動きが選挙という場であることが示唆されます。
以下は、少しマニアックな分析です。さらさらっと「終わりに」までどうぞ。
③地域比
こちらの図は、各党の総立候補者のうち、各地域にどのくらいの割合で立候補しているかを示しています。
自民党と希望の党、共産党は、政権を狙うべく全国にくまなく候補者をたてていることがわかります。
また、希望の党と維新の会の棲み分けにより、維新が東京に候補者を立てず大阪に比重が高くなっています。
公明党はもともと9名しか小選挙区に擁立していませんが、その多くは近畿からの出馬となっています。
立憲民主党は東京や南関東からの立候補が多いです。もともとリベラルが都市で強いと言われるようにリベラルの議員は都市部が多いことに加えて、希望の党との対立軸を明確にするために立憲民主党のもと戦うという戦略をとった候補者が多いとも言えます。
④拡大意欲比
こちらは、各党の立候補者数と、解散前の議員数(比例も含む)を示しています。
解散前議員数の中での自民党の圧倒的多数も注目に値し、前提として重要な事実です。
加えて、その解散前議員数と各党候補者数を見た時、過半数をとることができる可能性があるのは、自民/希望/共産の3党のみであることが一瞬で分かります。
⑤比例単独比
最後に、本稿①~③のデータ上の制約について、こちらで感じてください。
各党の立候補者のうち、比例単独で立候補している候補者の割合を表しています。
公明党、幸福実現党、こころの3党は比例単独候補者の割合が多くなっています。
そのため、以下2点をご注意ください。
・公明党と幸福実現党については小選挙区候補者で行った①~③の分析が候補者全体の分析と大きくずれてしまっている可能性がある。
・日本のこころは、①~③で扱えなかった。
なお、公明党については、支持母体である創価学会員を中心に固定票が見込めるため比例区に向いていることと、支持政党一位の自民党との協力関係があることが、比例重視の選挙戦略に繋がっていると見られます。
終わりに
以上で、①男女比 ②年代比 ③地域比 ④拡大意欲比 ⑤小選挙区/比例比 についての候補者分析を終わります。
国会は、1億2000万人を代表する機関としての多様性担保ができていますか?という観点を①②で提示しました。
有権者の皆様には、政策に加えて議員や政党の属性や傾向というものも判断材料に加えて投票をしていただけらなと考えて、このような記事を執筆しました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
その他分析すべき項目を募集しています。お気軽に声をお寄せください。