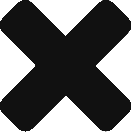ポイント
・歴史上,日本の総選挙はほとんどが解散総選挙であり,任期満了は1回だけ
・首相の解散権行使には,メリットとデメリットがあり,海外では最近デメリットを重視して,制度上解散権を制限する傾向にある
・首相の解散権は何十年も前から議論されてきたし,今回の選挙でも争点になりえたが,結局また下火になってしまっている
去る9月28日,衆議院は解散し,日本は一気に選挙モードへと突入しました。安倍首相は解散直後の記者会見で解散理由を「税の使い道について信を問うため」とし、この解散を「国難突破解散」と位置付けました。これに対して,野党は「大義なき解散」と反発。6月以来,憲法に基づいて求めてきた国会の招集がやっと決まった9月28日に,所信表明演説もせずに冒頭解散した首相を批判しました。
2014年以来の安倍首相による解散であり、当時と同じく「首相の解散権」について多方面から意見の出た解散権行使。大義のあるなしは,ポジショントークに終わってしまう無益なものです。本稿では,純粋な制度としての「首相の解散権」について,多角的な視点で検討してみようと思います。
日本の解散権行使の歴史
今回の安倍首相による衆議院解散は,日本国憲法施行から通算24回目の解散でした。
日本がこれまで経験してきた24回の衆議院総選挙のうち、任期を満了して選挙をしたのは1度のみ(1976年三木内閣)。それ以外の23回は全て首相の解散によるものです。その内訳は,憲法7条に基づく解散が19回,憲法69条に基づく内閣不信任案の可決による解散が4回であり、圧倒的に7条解散が多くなっています(それぞれの解説は後述します)。
この多数に及ぶ解散の結果,衆議院の任期は本来4年のはずが,戦後の衆議院の任期は実質的には平均2年半ほどになってしまっています。
しかし,解散とは,議員の任期が満了する前に,首相が議会を解散し,国民に対して「私たちのやることに同意してくれますか」と直接問うもの。したがって,本来であれば,民主主義の真骨頂のような制度であるにもかかわらず,なぜその行使が問題ありと考えられているのでしょうか。
解散権概要-69条型と7条型
まずは解散権の簡単な解説から。
日本の政治における「衆議院解散」には,いわゆる「69条型」と「7条型」の二つがあります。69条型とは「憲法69条に基づく解散であり,内閣不信任決議が可決されて内閣が解散を選択する場合」を指し,それ以外の解散を「憲法7条に基づく解散」とします[i]。
69条型とは,衆議院に内閣不信任決議が可決された場合,内閣が対抗策として衆議院を解散する形のもの。議院内閣制を採用する国ではほぼ全てこの型が導入されています[ii]。
他方で,7条型の解散を導くには,いくつかのクッションが必要です。憲法7条を見てみましょう。
日本国憲法7条3号
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
三 衆議院を解散すること。
この条文を素直に読めば,天皇が「衆議院を解散する」という国事行為を行うために,内閣が「助言と承認」をすることになります。しかし天皇は実質的な政治権限を持たないはずですから,実質的には内閣が(「助言と承認」というクッションを挟んで)衆議院の解散権を有するという解釈をするのです。
実際のところ,内閣不信任決議への対抗策としての69条型とは異なり,解散をする場合が限定されていない7条型に対して,政治家も官僚も学者も多数議論してきたのですが,実務上は7条型の解散権行使が運用として定着していったのでした。
解散権概要-首相の専決事項…?
もっとも,衆議院の解散権は上述したように「内閣」にあるはずです。なぜそれが「首相の専権事項」とか「首相の伝家の宝刀」と言われるようになったのでしょうか。そこには時代的な背景と制度的な理由がありました。
まずは時代的な背景として,長らく日本の首相は強いリーダーシップを発揮できない立場にあったこと。現代のように首相に人事権等が集中していなかった当時,首相にとって,反抗してくる自党内の勢力に対抗できる伝家の宝刀が「解散権の行使」だったわけです(議員にとって解散は失職を意味するわけですから,「解散してやるぞ」という脅しはとても良く効くのです)。
しかし,制度として内閣に解散権がある以上,首相が伝家の宝刀として解散権を行使するには,内閣を構成する全ての大臣の同意を得なければなりません(閣議は全会一致が慣習となっています)。しかし,大臣を選ぶのは首相であるため,反対した大臣はクビにしてしまえば済みます(実際に小泉首相の郵政解散はそのようにして閣議決定を経て衆議院を解散しました。
以上のような時代的,制度的理由から,衆議院の解散権は「首相の専権事項」として,「伝家の宝刀」となっていったわけである。
解散権を制限すべきではないか(一般論)
改めて,本稿の最初の問いに戻りましょう。本来であれば衆議院解散とは,国民に政権の是非を問うための民主主義の真骨頂のような制度であるにもかかわらず,なぜその行使が問題ありと考えられているのでしょうか。
一方で,首相による解散権行使を無制限にさせて良いという意見も存在します。仮に衆議院が解散の危機意識から解放され(議員にとっては解散とは失職を意味するため,解散は脅威です),任期の間は一切解散がないとすれば,衆議院は民意から乖離した政治を行うおそれがあります。だからこそ,内閣(実質的には首相)に自由な解散権を与え、衆議院に常に「解散があるかもしれない」と危機感を抱かせることで,衆議院の政治が常に民意に近づこうとするようになるという意見です。
しかし,どうやら昨今の選挙のやり取りを見ていると,「大義なき解散」と批判された歴代首相は,「大義はある」と常に反論していますから,「解散には大義が必要」という点で見解は一致しているようにも思えます。
また,参議院は解散がありませんが,かといって民意と離れている政治を行っているかというと,そういうことはこれまでのところ指摘されていません。衆議院が民意から乖離することより,首相が党利党略あるいは自己都合の解散権行使をすることによる弊害の方が大きいという認識が,政界にも広まっているようです。
解散権を制限すべきではないか(海外の例)
海外の例はどうなっているのでしょうか。
先進各国は解散権を制限する傾向にあり,OECD加盟35カ国で政権の自由裁量による議会解散が一般化しているのは日本,カナダ、デンマーク、ギリシャの4カ国にすぎません。
日本と同じ議院内閣制を採用するイギリス(実際,7条型解散の生みの親はイギリスです)では,2011年に制定された「議会任期固定法」によって,首相が(日本でいう69条型以外で)解散権を行使するには,議会の3分の2の制限が必要となりました。この背景には複雑な政党事情がありますが,要は,イギリス政府が「歳出削減」と「増税」という国民に不人気な政策をとらざるを得ない状況で,各党が党利党略で耳障りの良い政策に走ることなく、「財政再建」「景気回復」に取り組むための法律でした。つまり,議会を解散のリスクから解放することで,むしろ国民が嫌がる政策も責任をもって実施することができるということです。
また,日本と同じく議会選出の首相を持つドイツでは,憲法制定当時(1948年)から,厳格に解散権が制約され,これまでわずか3回の解散しかありません。半大統領制のフランスでも,現行憲法下における解散は5回であり,解散権の行使が非常にまれであることがわかります。
以上のように,やはり海外でも,首相の解散権をフリーハンドに認めるということはほぼなく,何らかの形で制約を置いて,議員が任期を全うできるようなシステムにしていることがわかります。
具体的な制約の議論について
制限の方法としては,
- 憲法を改正する
- 法律で規制する
の2つがあります。
衆議院の解散権限は,69条又は7条に基づくものですから,それを制約したいならば憲法を改正してしまうことが最も理に適っています。
Plan A 69条限定改憲プラン
これは,首相による解散権行使を69条型,つまり衆議院による内閣不信任決議に対する衆議院解散のみに限定するプランです。このプランは,首相による他の理由の解散を全く不可能にしてしまう点で,最も厳格な縛りとなります。
しかし,これでは本当に解散が必要な場合に解散できなくなってしまう可能性があります。また,69条型解散の悪用も可能で,首相が解散したいときに,与党と相談して議会に意図的に不信任決議を可決させ,恣意的に「対抗策としての解散」を行うことができるのです(ドイツ連邦議会ではかつてそのような運用が実際にされた例がありますし,日本の吉田茂首相も同じような解散を行って「馴れ合い解散」と揶揄されたことがあります)。
Plan B 議会の承認条項追加プラン
別のプランとして,首相は69条型以外にも解散をすることができるが,その場合には議会の承認(過半数でも3分の2でも)を必要とする方法が考えられます。これはイギリスが採用したもので,首相のフリーハンドの解散権を議会が制限することが可能です。
もっとも,解散前の衆議院は,与党だけで3分の2を超えていましたから,結局このような制限があったとしても首相が解散するといえば解散していたでしょう。
他にも,フランスのように前回選挙から一定期間は解散することができない等の制約プランもあります。ここまで憲法改正のプランを示しましたが,次はもう一段フェーズを下げて,法律による制約プランを考えてみましょう。
Plan C 解散前に議論を必須とするプラン
内閣の衆議院解散権が憲法の解釈として成立してきている以上,それを今の憲法を変更せず,解釈によって制限するのは解釈改憲にあたり,法律によって制限するのは憲法違反になります。そこで,解散権自体は制限せず,解散を行うにあたっての手続を規定するだけであれば,これは解釈改憲にも憲法違反にもあたりません。
そこで,Plan Cとして,首相が衆議院を解散すると宣言した場合に,必ず国会で党首討論を行う,あるいは数日間の議論を行って国民に趣旨を説明する手続きを設けるという方法が考えられます。これを経ることで,国民にも解散の理由や争点がより明確になり,選挙への移行も滑らかなものになるかもしれません。
解散権の議論は全く進んでいない
ここまで海外の事例も交えながら,首相の解散権の行使について,議論を整理してきましたが,故保利茂衆院議長40年前、次のように言っていました。
「(解散は)内閣の恣意によるものではなく、あくまで国会が混乱し、国政に重大な支障を与えるような場合に、立法府と行政府の関係を正常化するためのものでなければならない」
あれから40年,未だこの議論は深まらず,やっと今回の選挙で立憲民主党のみが首相の解散権を制限することに言及している程度です(希望の党は首相の解散権を憲法改正案とすることを述べていたようですが,結局は公約には入っていません)。
野党やリベラルメディアは,今回の解散総選挙を「大義なき選挙」と言いますが,過去19回もあった7条型解散の中に「大義ある選挙」などあったのでしょうか。党利党略を与党も野党も張り巡らせた結果の歴史ではなかったでしょうか。解散権の裁量行使をフリーハンドにさせているのは,最終的には国民がこれまで「大義なき解散」に対する争点整理をしてこなかった点にあります。嫌気が差したなら解散権の行使を制限する必要性を訴えなければなりません。
しかしながら,これは実際には綺麗事です。いくら国民が圧力をかけようとも,首相が自らの権限を小さくするような法改正を行うことは考えにくい。野党としてそれを公約に入れる政党が政権交代でもしない限りは,変化が起きるはずありません。このあたりに国民からの訴えの限界を感じてしまうことは事実です。解散総選挙を「大義なき解散」と揶揄して終わるのではなく,民主主義の真骨頂である「民意への問いかけ」に対して,どこまで食い下がって意思表示できるかが真剣に問われているのです。
[i] なお,本稿ではこのように首相の解散権行使を69条型と7条型に便宜的に場合分けするが,後述するように全ての衆議院の解散は天皇の国事行為として詔書をもって行われる。したがって,69条型を含む全ての解散は憲法7条に基づく詔書によってなされるが,ここでは説明の便宜のため,69条型と7条型に分けています。
[ii] そもそも議院内閣制とは,国会と内閣が密接な関係にある(議会が首相を選ぶ,閣僚の半数以上が国会議員でなければならない等)一方で,それが癒着関係ではなく,お互いを牽制し合う形で緊張関係のもとでの統治を進めていく統治制度ですから,議会と内閣はお互いに対抗策を持っていなければならないのです。